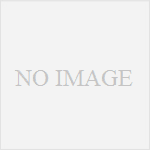蔓延するうつ病と精神医療の現在――北中淳子インタビュー:
以下の記事に異議があるので。その他にも多々あるが、今回は一点だけ。
-----
医療人類学者の北中淳子氏によると、現代はいわゆる「うつ病」の三度目の流行期だという。近代以降、この病を語る言説はそのあいまいな相貌を多種多様に変化させ続けてきた。かつては芸術家や知識人が罹る特権的な病とされていた「鬱」は、今や世界で普遍的と言っていい拡大を示している。著書『うつの医療人類学』でその浩瀚な知見からうつ病の考古学を展開した北中氏に訊いた。
※本記事は『エクリヲ vol.13』「鬱の時代へ――失調と回復の哲学」から抜粋掲載したものです
――全世界における新型コロナウィルスの感染者数が一億人を突破しました。一方、「世界の疾病負荷研究(GBD)」の調査によると、世界中のうつ病患者数は約二・六億人います。この増加ぶりの背景には「うつ」の概念の拡大があることを北中さんは『うつの医療人類学』で指摘されています。「うつ」が指し示す内容がいかに変化してきたか、その歴史を研究してきた先生は現在の状況をどうご覧になっていますか。
北中淳子(以下、北中) 日本とうつ病との関係について言えば、まず二〇世紀初頭に神経衰弱が大流行します(「〝うつ病〞の第一次流行」)。神経衰弱は現在のうつ病とかなり重なる部分が多い疾患なんですが、夏目漱石も「大学教授を十年間やったら神経衰弱にならないほうがおかしい」というようなことを語った(講演「現代日本の開化」)ように、知識人が近代化の波に飲まれて頭脳労働で神経を使い果たして罹る、過労の病として語られていました。それが徐々に市民の中に広がっていくと、神経衰弱は原因がはっきりとしない不定愁訴的な病に変わっていく。一九四〇年代には、当時の著名な精神科医たちが「最近、よくわからない症状を訴えられた医者は、大体みんな神経衰弱だろうで片付ける」と苦言を呈していたようです。もともとはエリートが限定的に罹る過労の病と捉えられていたのが、「過労ではなく人格の病、弱い者がなる病だ」という戦前・戦時期の変質論(うつ病を遺伝的、生態的変異と捉える説)と結びついた言説が出てくるようになり、徐々にスティグマ化されていきます。
その後、アメリカ由来の精神医学の影響から「神経症」という概念が導入され、日本でも神経衰弱のほとんどが神経症に置き換わっていく。その中で神経衰弱は医療が特に介入しなくても放っておけばある程度治る病気だ、医学の対象にしなくていいだろうという風潮が広がって一気に第一次流行は収まっていきます。
現代は三度目の「うつ」流行?
北中 一九五〇年代末に第一世代の抗うつ薬が発見され、日本にも導入されると二回目のうつ病ブームが一時的に起きます。新聞や雑誌などで盛んにうつ病について語られるようになり、「放っておけば大体三ヶ月から半年くらいで回復する病気だが、最近は良い薬も出ているのでよかったら精神科にも来てください」と精神科医が呼びかけるようになる。一九七三年には日本における精神分裂病(現在の統合失調症)に対するうつ病の比率がとうとう逆転し、外来の精神科診療でもうつ病が増加します。それぐらいメジャーな疾患になったんですね。
精神医学の歴史で繰り返されていることですが、新しい治療法ができると一時的にその方法が熱狂的に受け入れられたり、新しい薬の効果が想定より高かったりするんです。しかし、疾患がメジャーになることで診断を受ける層も多様化し、重症ではない人たちも薬を飲むようになる。すると当然、薬効が落ちてきて「思ったより効かない」という言説に反転する。抗うつ薬の時も同じことが起きて、抗うつ薬流行の反面、自然に治癒していたようなケースや神経症の人までもが薬を飲むことでかえって回復が遅れたり、慢性化していくケースも一九六〇年代には指摘されるようになるんですね。その頃になると抗うつ薬は決して万能ではないという言説が精神科医の間で広がり、精神療法的な試みがなされるようになります。ただし、医師が精神療法的に心理的洞察を深めようとして――患者の心理に関心を持ちすぎて――患者の人生に踏み入ってしまったがゆえに生じた医原病という側面もあると自己批判されもした。それ以降、うつ病の診療は心理的洞察を控えて、「真面目に頑張った結果としての病」として労い、あえて葛藤に蓋をする「小精神療法」が日本では主流になっていきます。
――薬でバイオロジカル(生物学的)に治すか、精神療法的に心に寄り添って治すか、という対立構図があったんですね。
北中 一九八〇年代にはDSM-III(アメリカ精神医学会作成の診断基準)で「メジャーディプレッション(大うつ病)」といううつ病概念がつくられ、従来のうつ病に加えて、それまで「神経症」として幅広くとられていた疾患も「うつ病」として書き直されました。「うつ病」とされる範囲が一気に広がったわけです。背景にはアメリカにおける精神療法派とバイオロジー派の戦いがあり、「神経症」と呼ぶと精神分析の対象でしたが、これを「うつ病」と呼び直すことでバイオロジー(生物科学)の対象に変えていったという経緯があります。
それに加えて一九八〇年代末、一九九〇年代にかけて新世代抗うつ薬が創られることで製薬業界とも結びついた世界的なマーケティングが行われ、「うつ病」の概念がどんどん拡散していく。これが三回目の流行だと思います。この時期は精神分析への批判が広まっていた時期でもあり、アメリカで医療が経済的に見直されていた時期でもありました。精神療法に対する保険診療を縮小したいという保険会社の思惑もあり、短期間で良くなり、マンパワーもさほど必要でない抗うつ薬治療を薦める動きが製薬業界の利益とも結びつき、「うつ病は精神療法を受けても良くならないけど、抗うつ薬を飲むと良くなる」というキャンペーンが始まっていく。
アメリカの場合は特に心身二元論が根付いていることから、うつ病は脳の化学物質の変調に過ぎず、個人の生き様とか性格を責めるべきではないとされ、アンチ・スティグマ化されています。北米の若者が今でも比較的気楽に抗うつ薬を飲んでいるのは、当時のキャンペーンの影響もある。この頃から、暗い性格や友達ができない、勉強ができないといった問題に対して、実存的に悩んだり、自己を高めていくのではない方向で、単純に脳の化学物質に働きかけることでより良い自己を手に入れようという、エンハンスメント・テクノロジーとしての抗うつ薬使用が広がっていきます。多くの科学者がうつ病と診断されたわけでもないのに向精神薬を研究の創造性を高める目的で使っている、という言説が流布したのも一九九〇年代でした。
――うつ病の流行は、うつ病はバイオロジカルに治療可能だとする考えの急拡大とセットだったと。
北中 その一方、時を同じくしてグローバルメンタルヘルス運動が盛んになります。死亡率だけで見ると精神疾患は重要な疾患とはなかなか見なされない。たとえば摂食障害は死亡率が高いですが、他の精神疾患は慢性化や自殺のリスクはあるものの、病自体で亡くなることはないので、これまで医療経済的、社会経済的にはそれほど重要だと思われてきませんでした。そこに、世界銀行とWHOとハーバード大学が組んで、DALY(障害調整生命年)という、疾患に対する新しい計測概念をつくります。どういうことかと言うと、病によって仕事や家事ができなくなると生産性が下がり、経済に損失を与えますよね。この生産性の損失という観点で社会に与える影響を基準に疾患を計り直したのがDALYです。そういう観点でみると、実はうつ病は心臓疾患に次いで二番目に社会に損失をもたらす病だということが明らかになった。以後、世界の指導者たちが精神疾患を重要な政治・経済的課題だと位置付けるようになっていきます。
製薬業界の「バイオロジカルにみんなを救済しよう」というキャンペーンとこのグローバルメンタルヘルス運動が結合し、それまでうつ病患者がほとんどいないとされていた地域にもうつ病の概念が拡散・輸出されていきます。九〇年代当時、南米のスラムにも抗うつ薬のポスターが盛んに張られたりしていた。それは商業的な契機として見なされると同時に、人道的なミッションとしての熱情をもって世界的に広まっていったという両面があったわけです。その点がこれまでのうつ病の第一次、第二次の流行とは大きく異なるところではないでしょうか。
蔓延する「うつ」と治療の倫理
――うつ病が広く認知されることで、誰もが薬を服用するようになった一方、ネガティブな側面もあります。北中さんはうつ病が大衆化されることの功罪についてどう捉えていますか。
北中 私は二〇年以上、精神科領域での調査を行っていますが、精神障害に関する漠然とした、ときにロマンチックなイメージが現場に入ると見事に裏切られるという経験をしてきました。なぜならそこで本当に重篤な病を患う方の姿を見るからです。重篤なうつ病の症状で石のように固まって動けないとか、本当はお金持ちなのに貧困妄想に苦しんで「私は破産して一切お金がない、だからここも治療費を払えないからすぐに出させてください」と繰り返す方たちにもお会いしました。希死念慮が強い方は「(死にたかったのに)どうして助けたんだ」と入院したとき怒り、抜け出して再度死のうとされるんですけど、退院する頃には「あのとき助けていただいて本当によかったです。私はうつ病だったんですね」と驚かれたりすることが本当によくありました。それほど明らかに正常とは質的な断絶がある現象こそが、一九九〇年代半ばまでの精神科医が対象としていた本来のうつ病だと思います。それ以外の失恋や受験の失敗などによる心理的な不調は抑うつ神経症として病院ではなくクリニックで診てもらってください、と当時は棲み分けが比較的はっきりしていました。
この垣根を取っ払ったのがDSM-IIIの「大うつ病」概念で、その功罪はさまざまあると思います。功績のひとつは、それ以前は敷居が高かった精神科の診断が一般に広まることによって、精神病状態まではいかないかもしれないけれど、このまま抑うつ状態を放っておくと自殺企図にもつながりかねない方々を早く救えるようになったことだと思います。あとは自己や自分の心をより丁寧に点検するようになり、頑張ればどうにかなるんだという精神論で向き合ってしまう人たちも減ったはず。病に対する共感が生まれることで、弱音をはいていいんだという社会ができつつあるように思います。
――うつ病のスティグマ性が減ったことによる好影響もあった。
北中 ただ、罪の面としては神経衰弱の時代から何度も言われてきたことではありますが、自分がうつ病なのかそうじゃないのか悩む人が非常に増えてきています。一九八〇年代、一九九〇年代前半頃だと、うつ状態が重篤化してから診療に来られる方が多く、その頃の三環系抗うつ薬は副作用も強く、貯めておくと大量服用による自殺のリスクもあるので、医師も「これは精神病なんだ」という覚悟をもって薬を出していたし、患者さんも「治したい」という必死の思いで訪れておられたと思います。しかし、二〇〇〇年代に広がった新世代抗うつ薬は副作用が少ないというのが売り文句で、それまでの薬と比べてとても使いやすかった。だから「うつは心の風邪」キャンペーンに惑わされ、単なる風邪かと思いきやなかなか治らない、かえって人生の問題とつながって深刻化してしまい、問題を精神医療化することで、人生が狂ったと感じている方々にも出会いました。
かつてエルンスト・クレッチマーという精神医学者が、うつ病を水量がすごく減った川のような状態として例えたことがありました。川の水量、すなわちエネルギーが減ると、川の底のゴツゴツした岩とか歪んでいる部分が見える。そうなると(医師は)ここの岩を削って平らにしてあげればもっとスムーズに流れるんだから、と思ってつい治したくなるんだけど、でもそれは心の外科手術であり、一介の臨床医がそうやすやすと試みてよいものではないと、私の出会った医師たちも述べています。人は誰しもいろいろな歪みを抱えて生きているけれど、水嵩が増して普通に流れていればその底にある歪みも気にならないわけですよね。だから、そこをあえていじくらなくてもいい。だけど病気になった人は「こんなに苦しいんだから、引き換えとして治ったらもっといい人生を歩めるべきだ」「もっといい人生を生きなくては」と過剰な意味や、向上、救済を求めてしまい、水嵩が減って大人しく休養しなくてはいけないときにその岩や歪みを取り除こうとして必死になったりする。しかし人生の問題はそう簡単には解決できないし、人はそう簡単に変われるものでもないので、かえって収拾がつかなくなる場合も増えているのかもしれません。
うつ病治療の現状
――軽症のうつ病を抱えた方が増えているなか、容易に治癒しない方もいらっしゃる現状があります。この軽症化、慢性化するうつ病と社会や医療はどう向き合えばいいのでしょうか。
北中 グローバルメンタルヘルス運動でも当初は抗うつ薬を世界中に配りさえすればOKみたいな言説が少なからずあったんですが、今ではガイドラインが書き換えられ、少なくともマイルドディプレッション(軽症うつ)に関しては抗うつ薬ではなく心理社会的介入を最初に行うことが原則になっています。にもかかわらず、日本ではなかなかそれが進んでいない現状がある。理由としては診療報酬の制度上、精神療法としてお話を聞いただけだと報酬が少なく、採算が合わないからお薬を出さざるを得ないクリニックが多いことだと思います。患者さんも病院にせっかく来たんだし、何も貰わないで帰ることに対して抵抗感を持っていることが多いから、お薬をついお願いしてしまう。お薬だけですっきりと治るケースももちろんありますし、その場合はいいのですが、そうでないケースは長期化して、複雑化してしまう。
――イメージでは日本よりもアメリカのほうがバイオロジカルに薬で解決する風潮が強いと思っていたのですが、実態はそうではないんですね。
北中 アメリカは二〇世紀前半から精神分析の影響が色濃く、特に第二次世界大戦をきっかけに精神分析家が社会のさまざまな場で起用されるようになった経緯があります。戦後NIMH(アメリカ国立精神衛生研究所)の調査では退役軍人など、社会適応に問題を抱えている人たちが多いという結果が出て、精神療法が広まっていった。一九八〇年代まで精神療法的な下地が作られる時代が続いていたんです。だから精神分析の用語である「抵抗」や「無意識」「抑圧」「防衛機制」という言葉は少なくとも大学教育を受けた人たちには知られていて、日常用語にもなっていました。
ただ、精神療法が一般化するなかで負の側面も現れ始めました。自閉症について「冷蔵庫マザー」という言説が出てきたんですが、それは「母親が冷淡で育て方が悪い、コミュニケーションの仕方が悪いから子どもが自閉症になった」というような粗雑な精神分析理論で、当時の母親に対して強い罪悪感を植え付けてしまった歴史があります。アメリカでは精神分析の影響力が強力過ぎたので、自閉症の当事者を持つ家族が自分たちで自助グループを作り、精神分析に対抗するような動きが出てきます。たとえば遺伝子研究をしている若手の学者を助成したり、自閉症児を持つ家族の遺伝子プールを研究機関に提供したり。親の態度や環境ではなく遺伝子が原因だということを学術的に証明してほしい思いが強く、精神分析に対して批判的な声もいまだに根強い。だからバイオロジーが呪いじゃなくて救いとして台頭したというバックグラウンドもアメリカにはあるんです。日本は逆に精神分析がほとんど影響を及ぼしておらず、その代わりに精神病理学の伝統が強かった。精神病理学はバイオロジカルな考え方が基盤にあります。
これは精神分析の零落についてのサブストーリーですけど、一九六〇年代後半からアメリカでLSD(幻覚剤)が流行しました。当時、若い精神科医たちがLSDや覚醒剤を試すなかで、簡単に幻聴や幻覚、妄想を体験できることに気づくんですね。その頃の有名大学医学部の教授陣はほとんど精神分析派だったわけですけど。もしLSDで簡単に幻覚が見えてしまうなら、実は幼年期の経験やトラウマはそれほど重要ではないかもしれない、精神障害は単なるバイオロジカルな疾患だろうと。
――エンハンスメント・テクノロジーは、精神分析への対抗として出てきたということなんですね。
北中 そうです。興味深いのは、抗うつ薬の台頭やうつ病の流行がアメリカでは精神分析派の終焉、バイオロジー派の覇権を表すものとして語られた一方で、日本では一九九〇年代、阪神淡路大震災以降「心のケア」の重要性が言われ出したこともあり、むしろ心の領域との関連で語られるようになったことです。日本では抗うつ薬の普及がバイオロジカルな還元主義に行くのではなく、むしろ心を語るための素材として広まった点が北米との大きな違いだと思います。
また、日本のうつ病についての言説で特徴的なのは、「過労だからうつ病になる」というバイオソーシャルな語りが台頭したことです。たとえば一九九〇年代の電通事件(入社二年目の男性社員が自殺した)では、「男性社員はメランコリー気質であり、自分で捌ききれる以上の仕事を抱え込んでしまった上に、プライベートな理由で覚悟の自殺をした」という企業側の主張に対し、「これは疲弊によってもたらされたうつ病による衝動的な死である」と遺族側が論を戦わせ、二〇〇〇年、最高裁で遺族側が勝訴しました。ただ精神医学内の論争では、その個人の元々の気質や性格によるものが大きいのか、それとも社会が問題なのかという問いの解決が十分になされたわけではなく、むしろ司法・行政領域の先導によって「過労うつ病」という概念が社会に広まっていきます。
当時、この現状について精神科医の方に話をすると皆さん驚かれていたのを覚えています。ストレスだけでうつ病になるという議論は当時の精神科医にとってはあまりにも単純な話だったからです。うつ病といった精神障害を考えるときには、精神科医は、その個人の性質と社会環境との相互作用を想定されるので。ストレスだけをうつ病の原因とすることは難しく、たとえば同じ人が同じストレスを受けても、日が異なればうつ病にならないかもしれないし、同じストレスを受けてもうつになる人とそうでない人がいる場合、これをどう考えればいいのかという問題がある。直線的・単一的な因果関係がなかなか結べないわけです。ただ、以前語られていたような執着気質やメランコリー親和型といった古典的性格論は、もはやリジッドすぎて時代にもそぐわない。それに代わる科学的説明が今はまだ出てきていない状態なんですね。そこでメディアとかが飛びついたのが「新型うつ病」で、「未熟な人格のせいだ」みたいなことが言われてしまっている。でも、これはあまりにも精神障害を道徳化してしまうし、新型と言われて喜ぶ人がいるかと考えると……どうでしょう、救いや気づきのきっかけとしては機能しないのではと思います。
〇うつ病は治されるべきか
――DALY指標の話がありましたが、うつ病の人が増えると社会全体の生産性が下がってしまうからなるべく早く治したほうがよい、とする考えは一見すると合理的にも思えます。一方、うつ病にならないために、ストレスチェックに引っかからないように、あるいは早く回復するためにレジリエンスを身につけなければいけないという、自己責任論や経済合理性一辺倒のネオリベラリズム的な抑圧につながる恐れはないのでしょうか。
北中 まず、前提としてうつ病にはならないほうがその人にとってもよくて、啓発活動含めて社会的に未然に防いだほうがいいだろうとは考えます。無論、うつ病になって自分の生き方を見直せてよかったと仰る方々は、私が調査した事例でもとても多かったですし、病自体にも意味があるとは思います。ただ罹っている間は本当に辛く、死を考えるほど追いつめられるし、ご家族やお子さんにまで影響があることを考えると、DALYのような指標や予防も大切だろうと思います。精神障害は外から見えないので、その辛さがなかなかわかりません。生産性を基準にすることで、見えない苦しみを可視化できたのなら、その点では評価すべきだと思います。
ストレスチェックも、自己の気づきや、部署全体でのケアにつながるなら大切な装置だと思います。ただ、一歩間違えると個人の監視につながる恐れもあります。二〇〇〇年代のうつ病の流行時には、精神科の医師たちは、企業の人事部の方からしょっちゅう「うつ病になりやすい人たちをスクリーニングするようなテストはありませんか」と聞かれていたそうです。当時はまだメランコリー親和型のような性格論が強かった時期でもあったので、作れなくはなかったはずですが、それを作ってしまうと日本企業でもっとも重宝されるような、真面目で勤勉で他者配慮的な人たちがまったく採用されなくなってしまうんですよね。
――皮肉な話ですね。
北中 電通裁判だけでなく、その後のトヨタ裁判でもそうです。自殺された故人は理想的なトヨタマンと言われるような、国体への出場経験もあるスポーツマンで、皆が尊敬しているような方だった。そんな人こそが、自分に重い責任を課して、部下を守ろうとして自殺に追い込まれてしまう構造が日本企業には残っているわけじゃないですか。だから、うつを否定することは日本社会が自らを否定することに等しいのではないでしょうか。むしろそのような生き方が称揚されてきた構造を見直さないといけない。
実際、産業にかかわる医師たちは、ストレスチェックを個人の健康診断のみならず、組織全体の健康診断として使い始めています。個人ではなく関係性の病、環境が産み出す病としてうつ病を捉えられるなら、ストレスチェックがネオリベラリズム的な抑圧にならず、未然に防ぐための有効なテクノロジーになるかもしれません。
創造性とうつ病
――文化の面ではどうでしょうか。ジェネレーションZと呼ばれる、一九九〇年代後半以降に生まれた世代の北米出身のアーティストのリリックには、向精神薬やメンタルヘルスに関するものが目立ちます。二十歳前後で亡くなるアーティストも多い。北中さんはご著書のなかで一九世紀末には作家や詩人がメランコリアと特権的に結びついていたとお書きになっていますが、現代の状況はどのように映りますか。
北中 精神障害は創造性と深く関わってくると思いますし、作家や芸術家に関する研究をみると、気分障害の有病率には一般人と比べて有意な差があります。それこそ古代ギリシャからメランコリアに陥らない天才はいないと言われていたくらいで、創造性は世俗的な次元を一歩跳び越えたところにあるのかもしれません。それは、ときには精神障害への危機の一歩手前にある経験かもしれません。若者、特に一〇代や二〇代の初めというのは、まだアイデンティティが完全に固まっていなくて、身体レベルにおいても日々変化している時期ですよね。自分の中の不確実性、まだ見ず知らずの自己と付き合っていかなければならない不安定さの中で、自分はこうであるというアイデンティティと、相手からはこう見られているんじゃないかということのズレにつねに悩む。精神障害は一般的に「関係性の病」と言われるわけですけど、自己との関係性、他者との関係性が不安定なときに、精神障害的なものに開かれることはさほど不思議ではないのかもしれません。
薬物とアーティストとの関係について言えば、戦後の神経衰弱の時代から多くが薬剤を飲んでいるんですよね。食糧難の時代に大量の仕事をしないといけない作家たちが「食べ物はないけどヒロポンはある」とどんどん打って生産性を高めていたり。
――坂口安吾がヒロポン常用者だったことを思い出します。
北中 そうなんです。でも、それが実は依存症をもたらすものだという事実が明らかになり、廃れていくという経緯があった。今回の抗うつ薬の流行にも同じような側面があって、一九九〇年代にプロザックは北米で「魔法の薬」「幸せの薬」「生産性を上げる薬」「性格を変える薬」と大々的に宣伝されて、それに惹かれてしまった若者が多かった。その弊害が二〇〇〇年代には意識されるようになって、ニューヨーク・タイムズでも「砂糖水のようなものになぜ我々は熱狂したんだろう」という内容の記事が出ています。だから、こういう流行は何度も歴史で繰り返されていますし、そこで得られたのかもしれない創造性は儚いものであり、結局は生産性を下げるものであるという認識は重要かなと思います。
〈参考文献〉
Depression | Cambridge Encyclopedia of Anthropology
https://www.anthroencyclopedia.com/entry/depression
-----
こうやって話を構成すれば売れるのかと思いつつ読む。
ただ
にもかかわらず、日本ではなかなかそれが進んでいない現状がある。理由としては診療報酬の制度上、精神療法としてお話を聞いただけだと報酬が少なく、採算が合わないからお薬を出さざるを得ないクリニックが多いことだと思います。
というような時代錯誤的な間違い発言はやめてほしいと思う。全知全能の人など期待していないけれども、「採算が合わないからお薬を出さざるを得ない」などというのは、どこをどう観察すれば出てくる話なのか、不思議である。子引き、孫引きのあやふやな元があって、それをみんなで繰り返しているうちにこのようなタイプの学者さんも繰り返すということなんだろう。
現在の制度について説明すると、厚労省は薬価管理については異常に厳しくて、仕入れ値に10%を乗せると、場合によっては赤字になる薬だってあるほどだ。仕方がないのでその場合は院外処方にするしかない。はっきり言って、薬を出せば出すほど手間がかかるだけだ。院外処方にすれば薬局はもうかるだろうけれども、それだと薬局の儲けの分を患者さんが損をしていることになる。厚労省は誰のために制度を設計したのか。
しかも、最近の新薬はべらぼうな値段で申請されて、認可されている。ここ最近でいえば、ジェネリック薬の供給が不安定になり、たとえばバルプロ酸が3年近く使えなかった。最近やっと供給され始めて安堵しているところだ。その他にも順番に欠品が続いて困っていた。厚労省としては、抗うつ剤はジェネリック一種類、抗不安薬もジェネリック一種類、みんな一粒9円くらいだからちょうどいいだろうというつもりなのか。その代わり、メーカーが力を入れているデエビゴとかベルソムラとかリリカとかはたっぷり儲けさせてあげるということらしい。エーザイとMSDとファイザーだ。役人さんから見れば、困る人が国民の何%かいるという程度のこと、節約のためには工場も停止でいいじゃないか、一休みしていなさいということなのだろうが、中にはバルプロ酸でないといけないという患者さんもいて、エクセグランでもダメ、ガバペンでもリリカでもトピナでもダメなんです。それは現状の薬理学では説明しきれないことだけど現実にそんな具合で困っているのだ。原末がインドから届かないとかいろいろあるのかもしれないが、厚労省が自分で認可して自分で薬価を決めている薬くらい、安定供給させるように指導したらいいだろうと思う。お金なんか安いもんですよね、厚労省が安くしたんだから一番よくご存じだ。グローバル経済だからと言って、安い原産国に頼ってしまえば、基本の薬さえ手に入らなくなってしまう危険がある。これも安全保障の一環である。国民の命を守るんだよね。ね。そうだよね。
消費税を最終的に負担しているのがクリニックだっていうのはおかしいと思う。最終消費者が支払うべきでしょう。「消費」税なんだから。クリニックは卸と患者さんの中間に立っているだけで、消費なんてしていない。それなのに消費税をクリニックが支払っている。こんなこともそんなこともみんな覆い隠してしまうために、厚労省と財務省はマスコミを使ってキャンペーンを続ける。学者さんはその意図をくみ取ってなのかどうか、単に勉強不足なのか、「採算が合わないからお薬を出さざるを得ない」という発言がどうして、どこから出てきて、訂正もしないで垂れ流されていて、これについてはやはり一言いっておかなければならないと思った。
精神医学の歴史で繰り返されていることですが、新しい治療法ができると一時的にその方法が熱狂的に受け入れられたり、新しい薬の効果が想定より高かったりするんです。しかし、疾患がメジャーになることで診断を受ける層も多様化し、重症ではない人たちも薬を飲むようになる。すると当然、薬効が落ちてきて「思ったより効かない」という言説に反転する。抗うつ薬の時も同じことが起きて、抗うつ薬流行の反面、自然に治癒していたようなケースや神経症の人までもが薬を飲むことでかえって回復が遅れたり、慢性化していくケースも一九六〇年代には指摘されるようになるんですね。その頃になると抗うつ薬は決して万能ではないという言説が精神科医の間で広がり、精神療法的な試みがなされるようになります。ただし、医師が精神療法的に心理的洞察を深めようとして――患者の心理に関心を持ちすぎて――患者の人生に踏み入ってしまったがゆえに生じた医原病という側面もあると自己批判されもした。それ以降、うつ病の診療は心理的洞察を控えて、「真面目に頑張った結果としての病」として労い、あえて葛藤に蓋をする「小精神療法」が日本では主流になっていきます。
というあたりも、怪しい。