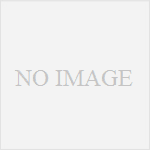下書き うつ病・勉強会#45 病前性格論のふくらみ中井

以下、中井久夫から引用採録。
『分裂病と人類』について
第一章の発表には、いささかの勇気を要した。もし、私が、自身のなかに「失調すれば分裂病となるもの」の種子を感じつつ、まとまった年月、精神科医として分裂病者といわれる人たちと相渉ってきたのでなければ、編集者門倉弘氏の、いささか異常なほどの奨めを別としても発表に踏み切ったかどらか、疑わしい。そもそも、発想が私のなかに生じ得たかも、また。一見理論的な形態を持ちながら、ほとんど個人的ときえ言いうるかも知れないほどに、もっとも経験密着的なものが、おそらく、本章であろう。(中井久夫『分裂病と人類』「あとがき」1982年)
「分裂病と人類」は分裂病の起源を、執着気質の起源を求めるのと同じ手法で探ろうとしたものである。しかし、分裂病の歴史の井戸はずっと深かった。歴史時代を越え、文化人類学の記述を辿ってついに着底したのは狩猟採集社会だった。かつてのエチオピア社会あるいはカラハリ砂漠の住人がいうS(分裂病)親和者の出番の社会だった。S親和者とは失調を起こさず少数者にも転落していないプレ分裂気質者である。
(……)
たまたま、私は、航空工学者・佐賀亦男氏の著書で、航空計器に使われている微分回路と積分回路の特性を読んだ。微分回路は徴候と傾向性を読む「時進み回路」(先取り回路)で、その特性はS親和者の長所と弱点とを一次近似として表わしているのではないか。私は膝を打った。しかも、この二つの回路は認知の基本的な二面を代表しているのではないか。予感と記憶である。これほど基本的なものなら失調しても人類から消滅はしないだろうと私は考えた。統合失調症患者の認知研究は積分回路的なものばかりを取り上げているから空を打っているのではないかとひそかに思った。もっとも、過去の経験を蓄積してノイズ吸収力の抜群な積分回路のほうの麻痺によっても似た事態が起こりうる。積分回路の弱さが発病か否かを決める可能性も併せて考えた。(……)
一言にしていえば、S親和者の優位性は「徴候を読む能力」にある。少くとも狩猟採集民族には欠かせない能力である。イタリアの歴史家カルロ・ギンズブルグが全く別の接近路から「徴候知」を抽出していたのとほぼ同時に独立して私も徴候知に市民権を与えたわけだ。この能力は、農耕社会の到来とともに重要性が減り、その結果、失調をおこしやすくなるかもしれないが、リーダーや気候や天災の予測に必要な能力である。雨司、呪術師はしばしば王を兼ねていたという。医師にも当然なくてはならない能力である。
しかし、職業生活だけがすべてではない。鬱病の場合と違う。徴候知は万人に必要であり、赤ん坊が母親の表情を読むことがすでにそうではないか。そして徴候的認知はとくに配偶者選択に有利である。相手が世俗的なことを考えているときに求愛しても成功はおぼつかない。状況や相手の表情や何やかやから「今だ」というタイミングを読む力は徴候知に属し、徴候知は「接合率」を高める重要因子である。だから、S親和者はなくならないーー。これはハックスリのよりもナイスな答えではないかと私は思った。
私の分裂病論の核心の一つは一見奇矯なこの論文にある。他の仕事は、この短い一分の膨大な注釈にすぎないという言い方さえできるとひそかに思う。S親和的な人、あるいは統合失調症患者の士気向上に多少程度は役ったかもしれない。家庭医学事典などは破滅的なことが書いてあるからである。(中井久夫「『分裂病と人類』について」2000年初出『時のしずく』所収)
正常者でもすべて分裂病症状を体験する
ここでは古典的「分裂病」概念を直接云々しない。…
分裂病に特異な症状が存在しないことについては次第に精神科医の合意を見つつある。…
オランダの臨床精神医学者リュムケは、正常者でもすべていわゆる分裂病症状を体験する、ただしそれは数秒から数十秒であると述べている。この持続時間の差がなにを意味するのか、と彼は自問する。
私は回復期において一週に一、二回、数十分から二、三時間、“軽症再燃”する患者を一人ならず診ている(慢性入院患者がごく短時間「急性再燃」を示すという報告も別にある)。なかでも、自転車で人ごみのなかを突っ走ると起こりやすい場合があるのは興味がある。当然、追いぬく人の会話の一句二句をひろって走ることになる。この切れ切れに耳に入ってきた人のことばは、それ自体はほとんどなにも意味しないのだが、いやそれゆえにと言うべきか、聴きのがせぬ何かの(たとえば自分への批評の)兆候となる。そこからさまざまな“異常体験”への裂け目がはじまる。しかし、じっとして“ふりまわされぬ”ようにしていれば、この兆候的なもののひしめく裂け目は閉じ、すべてが過ぎ去ることが判ってきて、そのようにしているとーーー決して愉快な時間ではないがーーーいつのまにか消えてゆく。この場合、ガラスにひびの走るように拡がって急速なパニックには陥らないわけで、どうやら多くの“分裂病性異常体験”は、その基底にある不安あるいは(対人的)安全保障喪失感(insecurity feeling)の“量”というか根の深さいかんで、恐慌状態になる場合からほとんど看過ごされる場合まで実に大きな幅があるようだ。幻聴でも、すこし聴こえただけで参ってしまう人もあるが、「大学教授なら停年までつとめられる例がある」とも聞いた。もっとも、持続時間を決定している因子はまた別かも知れない。
分裂病親和性:「ante festum(祭りの前=先取り)的な構えの卓越」
私は一方では、分裂病になる可能性は全人類が持っているであろうと仮定し、他方では、その重い失調形態ならば軽うつ状態をはじめ、心気症などいろいろありうると思う。
分裂病親和性を、木村敏が人間学的に「ante festum(祭りの前=先取り)的な構えの卓越」と包括的に捉えたことは私の立場からしてもプレグナントな捉え方である。別に私はかつて「兆候空間優位性」と「統合指向性」を抽出し、「もっとも遠くもっとも杳かな兆候をもっとも強烈に感じ、あたかもその事態が現前するごとく恐怖し憧憬する」と述べた(兆候が局所にとどまらず、一つの全体的な事態を代表象するのが「統合指向性」である)。(中井久夫『分裂病と人類』第1章、1982年)
非常時に社会の前面に出でるS親和者
奇妙なことは、無事平和のときには「隠れて生きることを最善」(デカルトの座右銘)とするS親和者が、非常時にはにわかに精神的に励磁されたごとく社会の前面に出で、個人的利害を超越して社会を担う気慨を示すことである。この「励磁現象」は史上数限りなくある。私は、サリヴァンについてこのことをやや詳しく述べたが、ニュートンもまた名誉革命に励磁されて国会議員となった一人であり、彼の物理学者としての活動はその時点で実質的に終わっている。ラッセルの諸活動はなお人々の記憶に新しいが、ラッセルが若き日に知的刺激を受けたライプニッツを「すぐれた知性の持ち主ながら王侯に取り入る人格成り下れる者」と罵倒しているのは、ほとんど近親憎悪に近い曲解である。なぜならライプニッツの努力は新旧両教会の和睦と統合にあり、それは十七世紀当時において、二十世紀のラッセルが直面した米ソ両大国の対立に等しい世界的大問題だったからである。
しかし、S親和者を「世直し」を唱える者として、「立て直し」路線に立つメランコリー親和者と対照させらるにしても、現実の世直し--革命--がS親和者によって遂行されるとするのは単純にすぎる。彼らのなかには革命の予言者もあるが、破局の予感に満ちみちつつ体制を守らんとする者もある。ただ、いずれにしてもS親和者が「歴史に選ばれた」気質の持ち主として行動するのは、問題解決者としてでなく主に問題設定者である。彼らは杏かな徴候から全体を推定し、それが現前するごとく恐怖しつつ憧憬する。(中井久夫『分裂病と人類』第1章、1982年)
S親和型の「兆候性への優位」/ 執着気質 の「現実から一歩遅れてあとを追う」
試みに、かつて私が執着気質を歴史的に位置づけるのに用いた手法を適用すれば、狩猟採集民においては、強迫性格もヒステリー性格も循環気質も執着気質も粘着気質も、ほとんど出番がない。逆にS親和型の兆候性への優位(外界への微分 〔回路〕 的認識)が決定的な力をもつ。ここでは「現実から一歩遅れてあとを追う」(ミンコフスカーー粘着気質者についての表現)ことであれ、「自縄自縛[インクルデンツ]」(テレンバッハーー執着気質者についての表現、訳語は木村敏による)であれ、遅れるものに用はなく、つねに現在に先立つ者であることだけが問題なのだ。……
”不意打ちに弱い”「無理の状態」
ここで、今日の分裂気質がただちに考えられてはならない。分裂気質とは、ちょうどかつて身体闘争などにおいて合理的な意味をもちえた高血圧が、今日の心理的圧力の優越した世界では単なる病気に転落したように、かつての有理性の大方を失い「少数者」に転落したS親和者が、みずからに馴染めない世界のなかでとる構えーー私が発病論においてみたところでは堅く剣を構える姿勢にたとえうる、それゆえ”不意打ちに弱い”「無理の状態」である。
私は少数者といった。それは必ずしも人口的な百分比を意味しない。私がいう多数者性は、執着気質者の記述がほとんど職業倫理のことば、またその少なからざるものが職業的美質とされることばで語られ、「執着気質的職業倫理」の抽出さえ可能であったことと対応し、少数者性は分裂病気質者の記述が一つの倫理を構成せず、分裂病者の記述は少なからず倫理的に中立的でない、ほとんどあらわに、負の意味を帯びた形容詞によって飾られることと対応している。それゆえ、うつ病者はあまりにも容易に社会に復帰し、そして再発をくり返すのに対して、分裂病者の社会 “復帰 “(はたして復帰であろうか加入であろうか)は多くの壁をのりこえねばならず、その最大の壁が「強迫的なるものを身につけること」の成否にあり、これはまことに彼らにとってへラクレスの業である。それにもかかわらず、多くの社会復帰事業は、分裂病経過後の、いわば鎧の糸の(少なくとも一旦は)ほころびた分裂気質者を執着気質者に仕立て直すことをめざしている。
分裂気質者といわず、強いていえば原分裂気質者という含意で私がS親和者の名を用いる理由を了解していただきたい。……
技術の一身具現性、「進退きわまるところにのぼってしまう」
私はここで人類が狩猟採集段階から山地農耕段階へ進み、いくつかの中間段階を経て工業化社会に至るのが進化だと考えているわけでもなく、その逆に狩猟民を美化するつもりもない。言えることの一つは、技術の一身具現性においては最古の段階がきわだって卓越していることで、現代はこの一身具現性を犠牲にしてかつての身体の持つ技能性をことごとく外化させた (だから、裸のわれわれはどうしようもない抜け殻的存在だ)。しかし、この過程、戦争を生み階級を生み地球表面の大規模な破壊を行なった過程は、はたしてホームランであるのかホームランとまがう大ファウルであるのか。人類はいくつかの本質的倒錯をへて人間となったのであり、ヴァレリーの『ロビンソン寓話』によれば一種の(自然界の)贅沢、倒錯、逸脱であって、この大いなる倒錯に比すればあるいは分裂病の”倒錯”など問題にならぬかも知れないことを、稀れには思いみてもよいであろう。…
強迫的な農耕社会の成立とともに、人間は自然の一部から自然に対立する者となったとは複数の人々の指摘するところだが、私はそれと同時に分裂病者が倫理的少数者となったと言いたい。このときから S親和者は、社会にみずからを押しつけようとすれば、「上」へ向かうより他はなくなったようだ。古くは王、雨司、呪医、新しくは数学者、科学者、官僚などに。当然、多くの失調者が予想されよう。ビンスヴァンガーが分裂病者のおかれている事態を形容した verstiegen とは「進退きわまるところにのぼってしまう」意というが、彼らの逃げ道は上にしか開かれていないのであるまいか。……
心の生ぶ毛
分裂病者の社会「復帰」の最大の壁は、社会の強迫性、いいかえれば強迫的な周囲が患者に自らを押しつけて止まないこと、である。われわれはそれを日々体験している。われわれは社会の強迫性がいかに骨がらみかを知っており、その外に反強迫性的ユートビアを建設することはおそらく不可能である。ただ言いうることは、私がかつて分裂病者の治癒は「心の生ぶ毛」を失ってはならないといったが、実はそれこそは分裂病者の微分(回路))的認知力であり、それが磨耗してはすべてが空しいことである。少なくともそれは、分裂病者あるいは S親和者から彼らが味わいうる生の喜びを奪うだろう。(中井久夫『分裂病と人類』第1章)
たまさかの治療場面で、治療者が感じる、慎しみを交えたやさしさへの敏感さにあらわれているような―――きわめて表現しにくいものではあるけれどもあえて言えば―――一種の「心の生ぶ毛」あるいはデリカシーというべきものは、いったん失われたら取り戻すことがむつかしい。
このことをわざわざ述べる必要があるのは、慢性分裂病状態からの離脱の途がどうも一つではないらしいからである。自然治癒力それ自体が、新しい、多少とも病的な展開を生む原動力となりうることは、自己免疫病や外傷性ショックをはじめ、身体疾患においては周知のとおりであるが、慢性分裂病状態からの離脱過程においても、一見、性格神経症、あるいは“裏返しの神経症”という意味でのいわゆる精神病質的な状態にはまり込むことが少なくない。
これらは、いわば「心の生ぶ毛」を喪失した状態である。「心の生ぶ毛」を喪失すること自体は何も分裂病と関係があるわけでなく、そういう人は世に立ち交っている人のなかにも決して少なくないけれども、「高い感覚性」をかけがえのないとりえとする分裂病圏の人にとって、この喪失の傷手はとくに大きい。
執着気質者におけるpost festum(事後=あとの祭)的な構え
このような社会との「折り合い」のむつかしさにもかかわらず、S親和者が人類の相当多数を占めることが、おそらく人類にとって必要なのであろう。かりに執着性格者のみからなる社会を想定してみるがよい。その社会が息づまるものであるか否かは受け取る個人次第で差があるだろうが、彼らの大間題の不認識、とくに木村の post festum(事後=あとの祭)的な構えのゆえに、思わぬ破局に足を踏み入れてなお気づかず、彼らには得意の小破局の再建を「七転び八起き」と反復することはできるとしても、「大破局は目に見えない」という奇妙な盲点を彼らが持ちつづけることに変わりはない。そこで積極的な者ほど、盲目的な勤勉努力の果てに「レミング的悲劇」を起こすおそれがある--この小動物は時に、先の者の尾に盲目的に従って大群となって前進し、海に溺れてなお気づかぬという。(中井久夫『分裂病と人類』第1章、1982年)
執着気質者は)カタストロフが現実に発生したときは、それが社会的変化であってもほとんど天災のごとくに受け取り、再び同一の倫理にしたがった問題解決の努力を開始する(……)。反復強迫のように、という人もいるだろう。この倫理に対応する世界観は、世俗的・現世的なものがその地平であり、世界はさまざまの実際例の集合である。この世界観は「縁辺的(マージナル)なものに対する感覚」がひどく乏しい。ここに盲点がある。マージナルなものへのセンスの持ち主だけが大変化を予知し、対処しうる。ついでにいえば、この感覚なしに芸術の生産も享受もありにくいと私は思う。(中井久夫『分裂病と人類』第2章、1982年)
次に付記として、1994年の「「詩の基底にあるもの」―――その生理心理的基底」の冒頭のいくつかの文章群を並べる。
精神分裂病における言語危機と詩を生み出す生理・心理的状態の相同性
1
精神科医として、私は精神分裂病における言語危機、特に最初期の言語意識の危機に多少立ち会ってきた。それが詩を生み出す生理・心理的状態と同一であるというつもりはないが、多くの共通点がある。人間の脳がとりうる様態は多様ではあるが、ある幅の中に収まり、その幅は予想よりも狭いものであって、それが人間同士の相互理解を可能にしていると思われるが、中でも言語に関与し、言語を用いる意識は、比較的新しく登場しただけあって、自由度はそれほど大きいものではないと私は思う。
言語危機としての両者の共通点は、言語が単なる意味の担い手でなくなっているということである。語の意味ひとつを取り上げてみても、その辺縁的な意味、個人的記憶と結びついた意味、状況を離れては理解しにくい意味、語が喚起する表象の群れとさらにそれらが喚起する意味、ふだんは通用の意味の背後に収まり返っている、そういったものが雲のように語を取り囲む。
この変化が、語を単なる意味の運搬体でなくする要因であろう。語の物質的側面が尖鋭に意識される。音調が無視できない要素となる。発語における口腔あるいは喉頭の感覚あるいはその記憶あるいはその表象が喚起される。舌が口蓋に触れる感覚、呼気が歯の間から洩れる感覚など主に触覚的な感覚もあれば、舌や喉頭の発声筋の運動感覚もある。
これらは、全体として医学が共通感覚と呼ぶ、星雲のような感覚に統合され、またそこから発散する。音やその組み合わせに結びついた色彩感覚もその中から出てくる。
さらにこのような状態は、意味による連想ばかりでなく、音による連想はもとより、口腔感覚による連想、色彩感覚による連想すら喚起する。その結果、通用の散文的意味だけではまったく理解できない語の連なりが生じうる。精神分裂病患者の発語は、このような観点を併せれば理解の度合いが大きく進むものであって、外国の教科書に「支離滅裂」の例として掲載されているものさえ、相当程度に翻訳が可能であった。しばしば、注釈を多量に必要とするけれども。
このような言語の例外状態は、語の「徴候」的あるいは「余韻」的な面を意識の前面に出し、ついに語は自らの徴候性あるいは余韻性によってほとんど覆われるに至る。実際には、意味の連想的喚起も、表象の連想的喚起も、感覚の連想的喚起も、空間的・同時的ではなく、現在に遅れあるいは先立つものとして現れる。それらの連想が語より遅れて出現することはもとより少なくないが、それだけとするのは余りに言語を図式化したものである。連想はしばしば言語に先行する。
当然、発語というものは、同時には一つの語しかできない。文字言語でも同じである。それは、感覚から意味が一体となった、さだかならぬ雲のようなものから競争に勝ち抜いて、明確な言語意識の座を当面獲得したものである。
詩とは言語の徴候的側面を主にした使用であり、散文とはその図式的側面を主にした使用である
2
詩作者と、精神分裂病患者の、特に最初期との言語意識は、以上の点で共通すると私は考える。
私がかつて「詩とは言語の徴候的側面を主にした使用であり、散文とはその図式的側面を主にした使用である」と述べた(『現代ギリシャ詩選』みすず書房、一九八五年、序文)のは、この意味においてである。この場合、「徴候」の中に非図式的、非道具的なもの、たとえば「余韻」を含めていた。その後、私はこの辺りの事情を多少洗練させようとしたが、私の哲学的思考の射程がどうしても伸びないために徹底させられずに終わっている(「世界における索引と徴候」『ヘルメス』 26号、岩波書店、1990年、「世界における索引と徴候 ――再考」同27 号、1990年)。「索引」とは「余韻」を含んでいるが、それだけではない。
その基底には、意識の過剰覚醒が共通点としてある。同時に、それは古型の言語意識への回帰がある。どうして同時にそうなのであろうか。過剰覚醒は、通用言語の持つ覆いを取り除いて、その基盤を露出すると私は考える。
言語リズムの感覚はごく初期に始まり、母胎の中で母親の言語リズムを会得してから人間は生れてくる。喃語はそれが洗練されてゆく過程である。さらに「もの」としての発語を楽しむ時期がくる。精神分析は最初の自己生産物として糞便を強調するが、「もの」としての言葉はそれに先んじる貴重な生産物である。成人型の記述的言語はこの巣の中からゆるやかに生れてくるが、最初は「もの」としての挨拶や自己防衛の道具であり、意味の共通性はそこから徐々に分化する。もっとも、成人型の伝達中心の言語はそれ自体は詰まらない平凡なものである。言語の「発見論的」 heuristicな使用が改めて起こる。これは通常十五歳から十八歳ぐらいに発現する。「妄想を生み出す能力」の発生と同時である。
言語の徴候的側面への過敏
3
実際、妄想は未曾有の事態に対する言語意識の発見論的使用がなければ成立しない。幼少年型の分裂病では、これを分裂病と呼べるとしてであるが、言語は水や砂のようにさらさらと流れて固まらない。しかし、妄想は単に言語の発見論的使用ではない。妄想が妄想として認識されるのは決してその内容ではなく、問題の陳腐な解決、特にその解決に権力欲がまつわりついた場合であり、さらに発語内容のみならず形式のほとんど一字一句に至るまでの反復によって「妄想」と認識される(初期分裂病の「妄想的」発語は妄想ではない)。妄想を、通常人が「奇想天外」と余裕を以て驚いてみせるのは、実はその意外性、未曾有性でなく、その陳腐さを高みから眺められるからである。もし陳腐でなければ(いやいささか陳腐であっても)、啓示として跪拝するのは日常見られることではないか(ここで分裂病が一次的には妄想病ではないかと私が考えていることを言っておく必要があるだろう)。
むろん一方は病いであり、一方は病いではないといちおうは言うことができる。しかし、分裂病の場合でも、その最初期、病いといえるか否かの「未病」の時期に言語の徴候的側面への過敏が顕著であり、また一般には、この過敏はその時期の徴候一般に対する過敏の一部として出現する。逆に、詩人の場合も、何の危機もなくて徴候性への敏感さが現れるかどうか。
散文を書く時は、たとえ難渋するにしても、それは主題との格闘であって、言語そのものに対しては「大地の感覚」を維持している。散文においても言語は「発見」の道具でありうるが、言語を「発見論」的にしようしてはいない。「発見論」的使用とは、発見のために闇を探ることであり、それは決して何かを証明することはなく、常に「悪魔と深い海との間に落ちる」危うさがある。詩とは言語の「発見論的」使用であり、それゆえの徴候あるいは余韻、索引への敏感性があるということができると私は考える。詩を書き始める年齢は「妄想能力」の成立の年齢とほぼ一致する。
かりに、貴重な薄氷感を失えば、言語の発見論的使用は「妄想」に堕する危険がある。実際、妄想は全面的危機に際して一つの解釈を示して救い手として現れるものであり、患者が妄想にその内容にふさわしい恐怖を示さないかに見えることは、何よりもまず、それに先行する事態がはるかにおそるべきものであって、それに比すれば何ほどのことはないからである。実際、妄想の反復性と一義性とは、内容の恐怖性を補って余りある安定を与える。ここに妄想の抜けにくさがある。それは不要になった時に自然に消滅する他はないものである。しかし、安んじて共存できるものでもない。また問題は、新しい体験が入ってこなくなることであり、それゆえに妄想を持つ人の「心が痩せる」。詩と妄想とは最終的には相互排除的であるが、出発点においては、まったく別個のものではないと私は考える。むろん、発見論的使用と無縁な韻文はありうる。それは韻文であるが「詩」との相違は、数学の論文とパズルとの差に近くはないか。もっとも、詩作のある段階においてはパズル的側面、言語ゲーム的側面が前に出ることもある。それが詩を完成させる救いになることもある。(中井久夫「詩の基底にあるもの」初出「現代詩手帳」第37巻5号、1994年5月)
「「もの」としての言葉」とあるが、これはラカン派では「言葉の物質性 motérialité」と表現され、ラカンのララングに相当する(参照:ララング定義集).
ララングは享楽を情動化する。…ララング Lalangue は象徴界的 symbolique なものではなく、現実界的 réel なものである。現実界的というのはララングはシニフィアンの連鎖外 hors chaîne のものであり、したがって意味外 hors-sens にあるものだから(シニフィアンは、連鎖外にあるとき現実界的なものになる le signifiant devient réel quand il est hors chaîne)。そしてララングは享楽と謎の混淆をする。…ララングは意味のなかの穴であり、トラウマ的である。…ラカンは、ララングのトラウマをフロイトの性のトラウマに付け加えた。…
現実界の症状、それは意味から切断されているが、言語からは切断されていない。現実界の症状は、「言葉の物質性 motérialité」と享楽との混淆であり、享楽される言葉あるいは言葉に移転された享楽にかかわる。(コレット・ソレールColette Soler、L’inconscient Réinventé, 2009)
ラカンは言語の二重の価値を語っている。肉体をもたない意味 sens qui est incorporel と言葉の物質性 matérialité des mots である。後者は器官なき身体 corps sans organe のようなものであり、無限に分割されうる。そして二重の価値は、相互のあいだの衝撃 choc によってつながり合い、分裂病的享楽 jouissance schizophrèneをもたらす。こうして身体は、シニフィアンの刻印の表面 surface d’inscription du signifiantとなる。そして(身体外の hors corps)シニフィアンは、身体と器官のうえに享楽の位置付け localisations de jouissance を切り刻む。(LE CORPS PARLANT ET SES PULSIONS AU 21E SIÈCLE、 « Parler lalangue du corps », de Éric Laurent Pierre-Gilles Guéguen, 2016)
なお、最晩年のラカンは言語は存在しない。ララングしかないとまで言っている。
私が「メタランゲージはない」と言ったとき、「言語は存在しない」と言うためである。《ララング》と呼ばれる言語の多種多様な支えがあるだけである。
il n’y a pas de métalangage, c’est pour dire que le langage, ça n’existe pas. Il n’y a que des supports multiples du langage qui s’appellent « lalangue » (ラカン、S25, 15 Novembre 1977)
以下の図の左側が言語にかかわる語彙群、右側がララングにかかわる語彙群である。
・象徴界は言語である。Le Symbolique, c’est le langage
・現実界は書かれることを止めない。 le Réel ne cesse pas de s’écrire (ラカン、S 25, 10 Janvier 1978)
もう一度ララングに戻ろう。
詩の吐露 Le dire du poèmeは、…「言語という意味の効果 effets de sens du langage」とララングという意味外の享楽の効果 effets de jouissance hors sens de lalangue」を結び繋ぐ fait tenir ensemble。それはラカンがサントームと呼んだものと相同的である Il est homologue à ce que Lacan nomme sinthome。(コレット・ソレール Colette Soler、Les affects lacaniens、 2011)
症状は言語の側にありsymptôme du côté du langage、…サントームはララングの側にある sinthome du côté de lalangue。(Myriam Perrin interviewe Pierre-Gilles Guéguen, 2016)
「「もの」としての言葉」あるいは「言葉の物質性 motérialité」とは、フロイトの「モノ表象 Dingvorstellungen」に近似しているとわたくしは考えている。
機知 Witze(言葉遊び Wortspielen)のひとつのグループにおいて、そのテクニックは、語の意味ではなく、語音 Wortklangへの心的態度の焦点化によって構成されている。(音声的)語表象 (akustische) Wortvorstellung 自体が、モノ表象 Dingvorstellungen との関係性を与えられることによって、意味作用 Bedeutung の代替となっているのである。(フロイト『機知』1905年)
最後にニーチェを引用しておこう。
言葉と音調 Worte und Töne があるということは、なんとよいことだろう。言葉と音調とは、永遠に隔てられているものどうしのあいだにかけわたされた虹、そして仮象の橋 Schein-Brückenではなかろうか。…
事物 Dingen に名と音調 Namen und Töne が贈られるのは、人間がそれらの事物から喜びを汲み取ろうとするためではないか。音調 Töneを発してことばを語るということは、美しい狂宴 schöne Narrethe である。それをしながら人間はいっさいの事物の上を舞って行くのだ。 (ニーチェ「快癒しつつある者 Der Genesende」『ツァラトゥストラ』第三部、1885年)
ドゥルーズ =アルトーならこうである。
いまや勝利を得るには、語-息 mots-souffles、語-叫び mots-cris を創設するしかない。こうした語においては、文字 littérales・音節 syllabiques・音韻 phonétiquesに代わって、表記できない音調 toniques だけが価値をもつ。そしてこれに、分裂病者の身体 corps schizophrénique の新しい次元である輝かしい身体 corps glorieux が対応する。これはパーツのない有機体 organisme sans partiesであり、吸入 insufflation・吸息 inspiration・気化évaporation・流体的伝動 transmission fluidique によって、一切のことを行なう(これがアントナン・アルトーのいう卓越した身体 corps supérieur、器官なき身体 corps sans organes である)。(ドゥルーズ『意味の論理学』「第十三セリー」1969年)
2019年12月18日水曜日
「大破局は目に見えない」という奇妙な盲点
国民集団としての日本人の弱点を思わずにいられない。それは、おみこしの熱狂と無責任とに例えられようか。輿を担ぐ者も、輿に載るものも、誰も輿の方向を定めることができない。ぶらさがっている者がいても、力は平均化して、輿は道路上を直線的に進む限りまず傾かない。この欠陥が露呈するのは曲がり角であり、輿が思わぬ方向に行き、あるいは傾いて破壊を自他に及ぼす。しかも、誰もが自分は全力をつくしていたのだと思っている。(中井久夫「戦争と平和についての観察」『樹をみつめて』所収、2005年)
……このような社会との「折り合い」のむつかしさにもかかわらず、S親和者が人類の相当多数を占めることが、おそらく人類にとって必要なのであろう。かりに執着性格者のみからなる社会を想定してみるがよい。その社会が息づまるものであるか否かは受け取る個人次第で差があるだろうが、彼らの大間題の不認識、とくに木村の post festum(事後=あとの祭)的な構えのゆえに、思わぬ破局に足を踏み入れてなお気づかず、彼らには得意の小破局の再建を「七転び八起き」と反復することはできるとしても、「大破局は目に見えない」という奇妙な盲点を彼らが持ちつづけることに変わりはない。そこで積極的な者ほど、盲目的な勤勉努力の果てに「レミング的悲劇」を起こすおそれがある--この小動物は時に、先の者の尾に盲目的に従って大群となって前進し、海に溺れてなお気づかぬという。(中井久夫『分裂病と人類』第1章、1982年)