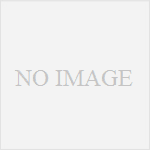量子力学における実在論と観測問題は精神医学においてどのような連想を誘うか 局所実在論
物理学においては観測問題は根本的に重要である。
量子力学の世界では、微小な粒子の物理量を観測する場合、観察主体が観察対象に影響を及ぼすことなく、その物理量を観測することは不可能であるとされる。測定しようとすれば観察対象に何かの影響を与えて、物理量が変化してしまうからだ。
このあたりのことは実在論を肯定するか否定するかの問題になる。実在論とは、測定する前にも、測定してから後にも、観察対象の物理量は存在して確定していると考えるものである。
賭場でさいころを壺に入れて振る。そして壺の動きがとまり、サイコロの目は確定する。その時点で各人は丁か半か賭ける。そして壺を取り除いて、サイコロの目が何であるかを一同が確かめる。
この時、サイコロの目が、確率的に重ねあわされて分布して存在しているなどとは考えない。
素朴実在論では壺の中のサイコロの目は、まだ観察していないだけで決定しているはずだ。
それが物理学でいう、Local realism 局所実在論の、局所論と実在論の、実在論の部分である。
つまり、観測してもしなくても、観察対象の物理量は確定している。
たとえば、あなたが月を見ていても見ていなくても、月の質量は変わらない。月の運動速度も変わらない。
あなたが月を見ていないとき、月がどのように存在しているかは分からないというならば、それは確かにそうだ。存在していることを証明するには観察しないといけない。しかし、観察以前の状態については何も言えないだろうと理屈では言える。
ところが我々の常識では、月という存在は人間の体験の時間の流れの中で、一定の客観的実在であり、質量や速度などは、一人一人の人間が月を見ていても見ていなくても、そんなことにはかかわりなく存在していることを理解している。そのようなものが実在である。錯覚や幻覚を排除している。
しかしそれは人間が肉眼で観察し、生身の肉体で経験する範囲の大きさの世界で当てはまる事実であって、量子論的な世界、つまり、電子、陽子、中性子などのふるまいを考える世界では通用しない。
局所論は、物理現象は局所的なものだということだ。ある場所で起きた出来事が他の場所のものに影響を及ぼすためには、間を光速以下の何かが伝わらなければならないとするもので、これが成立していなければ、因果律も成立しないことになってしまう。
局所実在論が量子力学の分野では成立していないと証明した2022年ノーベル物理学賞の対象となったのは、局所実在論によれば、
-2 ≦ 〈S〉≦ +2 (CHSHの不等式)
となるはずであるのに、これが破れていると実験的に証明したことである。
つまり、局所実在論は否定された。ということは、局所論か実在論かいずれかを否定しなければならないと考えられた。局所論を否定すれば、物理的な因果論が崩壊することになり、つまり、原因と結果の関係さえ不安定になってしまう。
例えば、太陽と地球はニュートンの言う万有引力によってお互いに運動しているので、例えば、太陽が吹き飛んで質量ゼロになったとしたら、地球の運動に大きな影響が出るのだが、その変化が生じるのは、太陽の質量がゼロになってからどの程度の時間が必要かと考えてみる。質量の変化が原因となり、引力の変化という結果になるためには、少なくとも、光が太陽から地球に届くまでの時間が必要である。
それが原因と結果である。光速を超える速度で影響が生じるなら、因果律を破壊するものとなる。
このことから、局在論は保護して、実在論を棄却する結果となった。
観察対象の物理量は、観測行為が実行される前は、確率分布として存在しているだけで確定していない、観察行為によって確定するものの、測定すると同時にその物理量は変化してしまう。
ーーーーー
というような解説を読みながら、物理学の観測問題や実在論の問題を参考にしつつ、精神医学のことを考えた。
精神医学では、観察対象において、精神医学的問題が発生しているかどうか、発生しているなら、どのような状態と考えられるか、それを探るのが診断であり、問題があるなら、それを解決できないか相談するのが治療である。
身体科ではたとえば肺炎でも大腸悪性腫瘍でも、観察行為にかかわりなく存在するなら存在するし、存在しないなら存在しないのであって、それは自明のことである。
ところが、精神科では、診断者の脳が観察対象の脳の状態を診断するのであって、診断行為は、診断者の脳にも変化をもたらすし、観察対象の脳にも変化をもたらす。
たとえば、対象者のビデオを診断者が見て、それだけから診断するというなら、観察対象の脳には変化が起こらないだろう。その場合も、診断者の脳には変化が生じている。
たとえばプレコックス・ゲフュールの場合、シゾフレニーの診断の手掛かりとなると論じられていたものであるが、これは、観察対象についての客観的観察内容や観察の結果の数字により診断するのではなく、診断者の脳に生じた変化を手掛かりとして診断することである。
つまり、診断対象の脳とシゾフレニーの脳が診断行為という局面に至ったとき、診断者の脳に何が起こるかを評価して、観察対象の脳の病理を判定するものであって、身体科には見られない独自の形式となっている。
またたとえば、一般に言われていることとして、成育歴で経験したことの構造が、現在の生活でも起こり、診察室でも起こると考えられている。これが三一致の法則であるが、ここでは成育歴の中で脳に刻まれた構造が、現在の生活でも再生され、診察室でも再生されると考える。それが観察対象の脳に刻まれた一貫した傾向であり、ある場合には性格の障害や神経症的症状となる。この場合、対象者の脳に刻まれた構造は一定であり、それが展開される場として、成育歴、現在の生活、診察場面の三つで共通して一貫した構造があると想定されている。
しかし、実際にはそんなはずはない。成育歴の中での心的外傷の場面の対人関係の構造と、現在の生活の対人関係の構造と、診断場面での人間関係の構造は違うからである。外部の構造が異なれば、対象者の脳の反応も異なるものになるのは当然である。それなのに、上記三つの場面で、観察対象の脳が同じ反応を呈するはずだとどうして仮定できるだろうか。
心的外傷の場面を発生させた対人関係は、現在の対人関係構造と、また診察場面での対人関係構造と、類似の面もあるし、相違している面もあるというのが実情である。それを大雑把に、ほぼ同じと考えれば、三一致の法則も成立するが、そうではなく、かなり違うと考えれば、それぞれでかなり違った反応を呈することもあるだろう。その場合にはうまく診断できないことになる。
まあ、理屈をこねれば、そうなる。現実には体験も現在の生活も診察室も大体一致するから、現状の考え方で問題はないと思うとしておこう。
診断行為を考えると、診断する側の脳と、診断される側の脳が出会っている。その場合に、侵襲性のない客観的な観察はない。どちらかが何か言葉をかければそこで反応が起こる。もはや意識の失われてしまった死体解剖の場合にはそのような反応は起こらない。
身体科の場合には、限られた場面ではあるが、心身症のメカニズムが関与し、診断行為が身体症状を変化させてしまうことになる。特に治りにくい病気の場合には心身症的メカニズムが働いてしまうので、注意が必要である。
精神科の場合にはそれが顕著に起こる。よい例は前掲のプレコックス・ゲフュールである。また昔から、関与しながらの観察などと言われる。そのようなものがあてにならないというものではない。治療者は自分という人格が患者の前で診断行為をした場合、患者がどのような反応をするのか、経験を蓄えている。それはある部分は治療者全体で共有できるものであるが、その他の部分は、その治療者の場合には、患者にそのような反応が見られるということであって、普遍性はないと考えられる。共通部分については書物で学ぶ。また先人から教えられて学ぶ。ところがその治療者に特殊な部分については自分で学ぶしかないところがあるだろう。
その特殊な部分がある種の患者には特異性の高い良い診断的手がかりとなるだろうし、別の種の患者には無効な診断的手がかりとなるだろう。
そうした事情をあえて考えず、身体科と同じ態度で客観的診断を試みるのが近年の診断学である。誰が、いつ、どこでやっても、同じ診断が下される、そのようなものを理想としている。
しかし、診断者Aが患者に睡眠はどうですかと聞くのと、診断者Bが患者に睡眠はどうですかと聞くのと、同じ部分もあるが、違う部分もある。違う部分にも多くの情報があり、診断的手がかりが内蔵されている。
人間の人格や性格、または脳の外部反応性は、場面に応じて非常に多面的である。たとえば意識障害の場合には、治療者の特異性などは抽象化できると思われる。しかし脳と脳が対話する場面では、どうしても、個々の特殊性が浮かび上がることになるだろう。そう考えると、内因性疾患であるシゾフレニーやバイポーラーでは診断者によらず診断はよく一致するが、性格障害や神経症の領域ではあまり一致しない場合があると思われる。それは診断が不正確なのではなく、非常に精密だからだ。
たとえば診断者が膝蓋腱反射を確認しようとする。それは胃カメラで診断しようとする行為と、精神科的診断場面との中間になるだろう。
個人的にはプレコックス・ゲフュールだけではなく、バイポーラー・ゲフュール、ニューローテッイク・ゲフュール、アノレクシア・ゲフュール、パーソナリティ・ディスオーダー・ゲフュール、ナルシスティック・ゲフュールも、あるだろうと思う。ただそれらは言語化しにくいので言語化していないだけだと思う。言語化するになじまない何かなのだ。一般化しにくい。共通体験としにくい。そのような領域が当然ある。
最初の診断も大切であるが、治療の進展に伴って見えてくるものもある。むしろその方が重要な情報だろう。しかしそれを治療者の共有体験とするにはまだ道は遠いだろう。
そしてそのようにして得られる全体を、病気と呼ぶべきなのかどうかについてはさらに留保が必要である。
-----
観察対象に、観察方法によらない、普遍の性質や特性数字が、観察以前にもあり、観察以後にもあるとと素朴に考えるのは、素朴すぎると思う。たとえば知能検査の数字は何を意味しているのか、もう一度考える必要があるだろう。観察対象の脳が呈する随意運動、不随意運動、言葉としての情報、あるいは語らなかったことの情報、それらはいつでもあるのか、観察前にもあったのか、観察以後は変化してしまうのか、いろいろ考える。
器質性部分は変化なく、非器質性部分は変化する。そしてそれらは同時に統合された形で提示される。それを分解して理解する必要がある。だから神経症性成分についての理解は必須なのである。
精神症状を呈している脳は、診察する前にも輪郭をくっきりと、唯一の性質を示しているものなのか、そうではなくて、診断者の脳と出会うことによって、ある特有の反応を呈し、それを手掛かりにその治療者は病気を診断し、治療するのか。
単純な連想であるが、物理学の根本問題に触れて、思ったこと。
-----
以上のような話はサリヴァンの関与しながらの観察で十分に述べられていることで、いまさら論じる必要もないのであるが、2022年のノーベル物理学賞の解説などに接して、外形的に類似していると思ったので、連想という形で書いた。
量子力学と精神医学が論理として内在的な関連を持つという話ではない。ただ、連想として考えられるような類似があるというだけである。
近年はロマン主義的・哲学的精神医学が排除され、そのことは誠に喜ばしい。そして生物学的精神医学が歴史上でも最高速度で前進している。まさに脳の世紀である。
しかしながら、他人の脳は測定可能で、時によらず、場所によらず、測定者によらず、確定した数値を示すのであるから、そのような客観的な数値を測定して、診断に役立てようとの考えは、まだまだ遠い目標であると思われる。
それはいずれ達成されるだろうが、まだしばらくの時間がかかるだろう。それまでの間は、我々は謙虚に、それは知ることができないものかもしれないと、量子力学の測定問題などを思い出してみるのもよいのではないかと思う。
現状で、脳波など客観的測定方法はあるとはいうものの、そのことと、思考内容や感情とはまだ少し隙間があるように思う。その隙間が非常に薄くなっているのは事実なのであるが。
しばらくは、診察室で、診断者と患者が何か話すということになるだろう。その時起こるのは、客観的で普遍的な、患者に内在する性質が数字として表現されるのではないことが重要である。
診断者と患者の脳が出会い、ある種の反応をして、診断者の脳にも影響が生じ、患者の脳にも影響が生じる。その場合は、診断者の特性をまず確認して、その診断者の場合には、患者の脳はどのような反応を呈するものか、理論化できれば良い。できないならせめて統計的な傾向として把握しておくのがよい。
そのような診察室での反応は、一般化できないものだから、方法として共有化することが困難である。その限界をまず確認しようということだ。
量子力学の場合は、確率を使って、驚くべきことに、現実の測定とよく合致する理論を組み立てることができた。
量子的サイズの物体は確率論的に存在し、測定しようとすれば、そうした確率論的な存在の仕方は終わって、具体的な数字になる。箱に入った猫は、箱に入っている状態で、つまり観察前には、確率論として存在している。そしてそれを現実に観測した時に、生きているか死んでいるか決まるという、実に人間の何十万年も続けてきた認識の基礎を変更するよう迫るものである。アインシュタインはじめ、いろいろな人が、そんなことはないだろう、人間の知識が不完全なだけではないかと論じた。実際私もそう思う。しかし実際に、実験によって、ベルの不等式は否定された。やはり、量子サイズの世界では、我々の伝統的な感覚は訂正が必要ということだ。
脳が脳を診断するという局面では、何か特殊なことが起こっているのだろうか。それとも、まだ科学として未熟なだけなのだろうか。そうした問いは、量子力学の観測問題や実在論問題に似ていると思う。精神医学の場合には、この先どちらに行くのだろうか。
診断者の脳が、患者の心臓を診断するときは、科学の方法で問題がない。それは当然である。一方、診断者の脳が、患者の脳を診断するときは、それでいいのか、それでよくないのか。
そういう問題もありそうだと言いたい。量子力学の場合は、アインシュタインが、量子力学は理論として不完全だから、そのような測定問題や不確定性などを言っているだけで、いずれ正しい理論に到達すれば、実在論は実在論であり正しいし、局所論は局所論であり正しいはずだと主張した。それが理論的にも、また今回は実験的にも、実在論を捨てる必要があると証明された。精神医学においても、そのような転換が生じる可能性があると言いたい。
同じことを何度も繰り返して申し訳ない次第である。