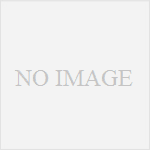心とはいったい何なのか。アリストテレスの時代以来の思想家たちは,心が最初は白板(タブラ・ラサ)の状態であり,そこに経験が書き込まれていくと想定した。
この〈外から内へ〉の見方では,脳の基本的な機能とは,外界の信号を知覚して,それを正しく解釈することである。だとすると,その信号に応答する操作が別に要るはずだ。つまり,知覚入力と出力の間に,環境からの感覚的表象を受け取って,何をすべきかを判断して行為につなげる仮想的な中央処理装置が必要となる。
現代神経科学のフロンティアはこの中央処理装置を探し出し,意思決定の神経メカニズムを体系的に探ることにある。しかし,よく検討すると,この枠組みは保持できないことがわかる。
問題は,網膜に到達した光子が「ひと夏の思い出」にどう変換されるのかを説明できないことだ。感覚器官の受容体が光や音などによって刺激された結果,神経細胞の発火パターンが変わるとしても,この変化自体が,脳内に取り込まれ統合されうる何かを「表現」しているわけではない。
たとえばバラの画像に反応する視覚野の神経細胞は,それ自体が花を「見る」わけではない。網膜からの複数の複雑な経路を含め,脳の他領域からくる入力に反応して電気的な振動を生み出しているだけだ。
そのため,入力と出力の間に,脳内の変化と外界の事象を観測し脳内の神経発火パターンに意味を与える実験者が必要になる。しかし,脳内にそうした翻訳者はいない。自らの発火パターンの変化を何が引き起こしたのかを,神経細胞自身が知ることはない。
一方,別の見方によれば,脳内ネットワークの主な任務は脳内のダイナミクスを維持し,意味を持たない膨大な神経活動パターンを生成し続けることにある。
はじめはランダムに見える行為でも,それが個体の生存に役立つものであれば,その行為を生み出した神経パターンは後から意味を獲得する。たとえば「テーテ」と言う赤ちゃんに,親が喜んでクマのぬいぐるみを渡すと,初めてその音が「テディベア」という意味を持つようになる。
近年の神経科学の発展は,この〈内から外へ〉というべき枠組みを支持している。
続きは日経サイエンス2023年10月号誌面で。