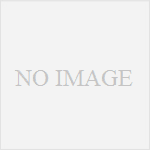うつ病とは、精神的なエネルギーが極端に低下して、ひどく憂うつな気持ちが続いたり、何をしても楽しいと感じられなくなったりして辛くなっている状態である。その辛さを、「泣き出す前に胸が締め付けられるような感じが、何日も何週間も、場合によっては何ヶ月も続いているようだ」と表現した人がいるが、それがこころの中で起こっていて外から見えないだけに、他の人にわかってもらえないというつらさも加わる。
うつ病など精神科の病気の原因についてはずいぶん研究が進んでいるが、まだまだその本体は解明できていない。そのために、精神疾患に関しては、ある症状群のために苦しい思いが続いている場合に、その症状に基づいた診断名をつけることになっている。熱が出ている、痛みが強い、というのと同じように、精神的なエネルギーが低下している状態にうつ病と名前をつけるという約束事になっているのである。
世界的に使われているアメリカ精神医学会の診断分類操作的診断分類『精神疾患の診断・統計マニュアル第 5 版 DSM-5』1)は厳密な診断基準を採用していて、うつ病と診断するには、1抑うつ気分、もしくは2興味や喜びの著しい喪失のいずれかひとつを含む、3食欲の減退または増加、4睡眠障害(不眠または睡眠過多)、5精神運動の障害(強い焦燥感・運動の制止)、6疲れやすさ・気力の減退、7強い罪責感、8思考力や集中力の低下、9死への思い、の 9 つの症状のうち 5 つ以上が、ほぼ毎日、ほぼ 1 日中存在している必要があるとしている。
しかも、これは必要条件であり、十分条件ではない。それに加えて、そうした症状のために本人が著しい苦痛を感じているか、生活に著しい支障を来すようになっているか、どちらかの条件を満たしている必要がある。うつ病と診断するためには、症状だけでなく、障害の程度も同時に評価しなくてはならないのである。しかも、抑うつ症状が双極性障害やパーソナリティ障害など、他の障害による可能性も評価しなくてはならない。
また、かりにうつ病と診断されたからいって治療方針が決まるかというと決してそうではない。それは、うつ病などの精神疾患が単一の要因による疾患ではなく、複数の要因が関与した症状群だからである。
うつ病概念が歴史上最初に用いられたのは紀元前5 世紀のヒポクラテスによる「メランコリア(melancholia)」である。メランコリアとは黒胆汁を指し、これが過剰になると、元気がなくなり、身体愁訴を引き起こすと考えられていた。その後、うつや躁は医療の世界から無視され続けたが、近世の18世紀に入り、身体的な原因を欠きその原因が心理的なものとして神経症が Karen により定義付けられ、メランコリーは神経症と区別されるようになっていった。
続いて Kraepelin が登場し、現在の抑うつ症候群の原形である躁状態とうつ状態をあわせて「躁うつ病」という一元論的疾患概念を提唱した(1913年)。 Kraeplin は精神障害を成因別に「内因性(外からの成因によらず素因により自発的に発症したもの)」「心因性(いわゆる病前性格や環境が強く関係したもので、神経症性や反応性を含む)」「器質因性(いわゆる身体疾患や薬剤によるなど症状性も含む)」に区分した。
一方、Leonhard らは、うつ相と躁相を繰り返す人と抑うつ相のみしか示さない人がいることから、単極性(unipolar)/双極性(bipolar)の極性に基づく二分法を提唱した。1966年には、Angst と Perrisが遺伝研究を通して、うつ病(単極性うつ病)と躁うつ病(双極性障害)の違いを明らかにしたこともあって、二元論的疾患概念がうつ病概念の主流となっていった。
1980年に発表されて世界的に使われるようになったアメリカ精神医学会の診断分類『精神疾患の診断・統計マニュアル第 3 版(DSM-III)』でも二元論が踏襲され、「気分障害(mood disorders)」のもとにうつ病性障害(depressive disorders)と双極性障害(bipolar disorders)が含まれた。DSM-3 は、精神疾患の生物学的原因が解明されていないことから成因別の分類ではなく、症状の特徴に基づいた分類が採用され、現在でもそれが主流となっている。
2013年に出版された DSM-5 では、双極性障害が抑うつ性障害と比べて統合失調症に近いという遺伝学的知見が集積されてきたことから「気分障害」の項目が消え、「抑うつ障害群(depressive disorders)」と「双極性障害および関連障害群(bipolar andrelated disorders)」が独立して記載されることになった。
DSM-5の「抑うつ障害群」は、双極性障害に近いものから 1 .重篤気分調節症、 2 .うつ病、 3 .持続性抑うつ障害(気分変調症)、 4 .月経前不快気分障害、 5 .物質・医薬品誘発性抑うつ障害、6 .他の医学的疾患による抑うつ障害、 7 .他の特定される抑うつ障害、 8 .特定不能の抑うつ障害に並べられている。このうち重篤気分調節症、持続性抑うつ障害(気分変調症)、月経前不快気分障害、特定不能の抑うつ障害の 4 つの下位分類は、DSM-5から新しく追加されたものである。
( 1 )重篤気分調節症 重篤気分調節症(disruptive mood dysregulation disorder)は、おもに12歳までの子どものために作られた診断分類であり、言語的・行動的に表現される感情の爆発が頻回である状態で診断される。有病率は不明であるとされつつも、 6 ヶ月- 1 年有病率は 2 - 5 %と推定されている。併存症が極めて多いのが特徴であり、その中でも最も多いのは反抗挑発症とされる。
( 2 )うつ病(DSM-5)/大うつ病性障害 一般的に『うつ病』と呼ばれる状態であり、うつ病(major depressive disorder)は、持続的な抑うつ気分、興味または喜びの喪失、倦怠感などの心的感情や身体感情のみならず,不眠や食欲低下など身体症状をも含む多様な臨床徴候より特徴づけられる精神疾患である。DSM-5 の診断基準では抑うつ気分または興味・喜びの喪失のいずれか、またはその両方の中核症状と、 4 つ以上の精神・身体症状が、 2週間以上ほとんど毎日持続し、そのために著しい苦痛もしくは顕著な社会・職業等の機能障害を引き起こしている場合にうつ病と診断される。鑑別診断としては、双極性障害、他の疾患による気分障害、物質・医薬品誘発性抑うつ障害または双極性障害、ADHD、適応障害、正常な悲嘆反応などが挙げられる。
( 3 )持続性抑うつ障害(気分変調症) 持続性抑うつ障害(persistent depressive disorder [dysthymia])は、DSM-IV の気分変調症にDSM-IV で定義された抑うつエピソードが 2 年以上持続する慢性の大うつ病性障害を統合したものである。持続性抑うつ障害のバリエーションとしては、うつ病が持続性抑うつ障害に先行することものもあれば(持続性抑うつエピソードを伴う)、先行する2 年以上持続性抑うつ障害はあったが、現在は抑うつエピソードを満たすもの(間欠性抑うつエピソードを伴う、現在エピソードあり)などがある。また、抑うつエピソードが少なくとも 2 年以上持続し、現在も抑うつエピソードが存続している場合は「持続性抑うつエピソードを伴う」特定用語が付記される。持続性抑うつ障害は、大うつ病性障害に比べて治療反応性に乏しく、虐待など幼児期のネガティブなライフイベントとの関与も指摘されており、いわゆる治療抵抗性の一群である。特に早発例(21歳以前発症)ではパーソナリティ障害群や物質関連障害が併存するリスクが高い。
気分変調症と抑うつエピソードが 2 年以上持続する慢性の大うつ病性障害を統合するのか。なぜ?
( 4 )月経前不快気分障害 月経前不快気分障害(premenstrual dysphoric disorder, PMDD)は、月経周期における気分の不安定性、いらだち、抑うつ、不安などの症状が月経の開始前に存在し、月経開始後の数日で改善し、月経終了後に最小化もしくは消失する状態である。診断には、患者の回想する症状ではなく、 2 ヶ月間の前方視的に症状評価によって確認することが必要である(ただし、診断はこの確認に先立ち暫定的に下されてもよい)。月経のある女性における12ヶ月有病率は1.8〜5.8%といわれ、初潮の後であればどの時期でも発症しうる。また閉経が近づくにつれ症状が増悪することもあるが、閉経後には症状は消失する。またストレス、対人関係での外傷体験、季節の変化、女性的に振る舞うことへの社会文化的側面、とくに女性的の行動に関する社会的役割などがPMDD の発病と関連した環境因子とされている。
( 5 )物質・医薬品誘発性抑うつ障害 物質・医薬品誘発性抑うつ障害(substance/medication-induced disorder)は、薬物・向精神病薬の摂取により引き起こされる抑うつ症状を特徴としている。物質の使用中止により、その物質の半減期や離脱症状にも影響はうけるものの、通常数日から数週間以内に症状は改善する。もし、予測より 4週間以上症状が持続する場合には、抑うつ症状を引き起こす他の要因を探す必要がある。物質であればアルコールや麻薬類など、医薬品であれば、抗ウイルス薬、心血管作動薬、副腎ステロイド、経口避妊薬、性腺刺激ホルモン薬、インターフェロンなどが起因となりうる。起因薬物の使用中止が原則であるが、実施困難な場合が多い。また他の抑うつ障害との合併や自殺リスクの増加、薬物療法への治療反応が悪いことなどが治療上は重要になる。
( 6 )他の医学的疾患による抑うつ障害 他の医学的疾患による抑うつ障害(depressive disorder due to another medical condition)は、身体疾患が抑うつ症状を引き起こすときにこの診断名がつけられる。誘因となる身体疾患に関しては、脳卒中、ハンチントン病、パーキンソン病、頭部外傷、神経内分泌疾患(例:クッシング病、甲状腺機能低下症)などが挙げられる。鑑別診断としては、抑うつ気分を伴う適応障害が挙げられる。
( 7 )他の特定される抑うつ障害 他 の 特 定 さ れ る 抑 う つ 障 害(other specified depressive disorder)は、抑うつ症状があり臨床的に意味のある機能障害を伴っているものの、抑うつ障害群の診断基準のいずれにも完全には満たさない場合にその特定の理由を添えて診断が下される。「他の特定される」という用語を使用して以下 4 つの特定できる症状例が示されている: 1 .反復性短期抑うつ(毎月 1 回 2 -13日のうつエピソードが12ヶ月以上にわたり存在)、 2 .短期間の抑うつエピソード( 4 -13日の抑うつエピソード)、 3 .症状不足の抑うつエピソード(抑うつ感情とその他 1つの症状が 2 週間以上持続する)。
( 8 )特定不能の抑うつ障害 特定不能の抑うつ障害(unspecified depressive disorder)は、上述の「他の特定される抑うつ障害」とほぼ同様の内容であるが、自殺企図後の救命救急室などや、診察回数がまだ少なく情報収集が十分でない段階において暫定的な診断名としてこの診断がつけられる。たとえば初診で抑うつ症状を呈する患者を診るとき、一次性のうつ病なのか、アルコール性の抑うつなのか薬物の副作用によるものなのかは、情報収集が十分でないとその判断はできないことも多い。このような状況下では、臨床像がはっきりするまでは、性急な診断を行って不必要な情報提供を行い患者や家族を混乱させ、また不適切な治療を実施しないためにも治療初期では暫定診断を下す意義がある。しかし、この特定不能の診断を下すことは、それで十分と妥協するのではなく、包括的な評価を進め、適切な診断に至るよう努める。
抑うつ症候群の特定用語 特定用語は、うつ病の特徴を補完するために使われる用語であり、従来のメランコリアの特徴を伴う、非定型の特徴を伴う、精神病性の特徴を伴う、緊張病を伴う、周産期発症、季節型に加えて、不安性の苦痛、混合性の特徴が DSM-5 から新しく加わった。
それぞれに複雑な歴史をもった言葉が並んでいます。
( 1 )不安性の苦痛を伴う これは診断名の前につける特定用語(specifier)であり、緊張感や落ち着かない感覚、心配事による集中困難、恐ろしいことが起こりそうな恐怖、自己コントロールの喪失感のうち 2 つ以上の症状を伴うときに記載する。この特定用語を有する患者は、自殺リスクが高いこと、罹病期間の長さ、社会復帰への困難さなどとの関連が示されている。
確かにね、neurotic。
( 2 )混合性の特徴 抑うつエピソードに加えて、気分高揚、自尊心の肥大、多弁、観念奔逸、活力・活動の増加、まずい結果になる活動への熱中、睡眠欲求の減少などの躁症状のうち 3 つ以上の症状が伴ったときにこの特定用語を使用する。抑うつエピソードに関連する混合性の特徴は、双極I型障害または双極II型障害に発展する大きなリスクファクターであることがわかっており、治療計画および治療反応をフォローアップするうえでこの特定用語の存在に注意することが臨床的に大切であると考えられている。
混合性は事実上バイポーラーでしょう。
うつ病の診断に当たっては、血液や脳波などの客観的な生物学マーカーが存在しないこともあって、DSM の診断基準を使っても臨床医によってかなりのばらつきや誤解があるのが現状である。そのために様々な混乱が生じているが、なかでも「適応障害」といわゆる「新型うつ病」(「現代型うつ病」「逃避型うつ」)という診断名には様々な問題が存在している。
適応障害 DSM によれば、うつ病性障害は、「著しい“抑うつ気分”あるいはほとんどすべての活動における“興味または喜びの喪失”のいずれか 1 つがあることに加え、強い睡眠障害や食欲低下の障害、自責感などの含めて 5 つ以上の診断基準をさまざまな症状を伴い、これらが 2 週間以上ほぼ 1 日中、毎日続いている状態」で、「臨床的に著しい苦痛または社会的、職業的、または他の重要な領域における機能の障害を引き起こしている」状態と定義される。一方、適応障害は、はっきりとしたストレスを契機にうつや不安、行動障害を発症して、気分障害やその他の不安障害などの診断基準も含め、どの精神疾患の診断基準も満たさない場合に診断される。
どの精神疾患の診断基準も満たさない場合という定義って、どうなんでしょう。
しかし、精神科医によっては、この区別が曖昧なまま「ストレスがあるから適応障害、ストレスがないから大うつ病性障害うつ病」と、ストレスの有無を基準に考える人がいる。確かに適応障害の診断には、疾患の発症に関与したと思われる明らかなストレスが存在することが大前提とされている。しかし、うつ病でも初発のエピソードではストレスが関与していることがほとんどであり、ストレスの有無だけでこの 2 つの疾患を分けることはできない。
それはそうだ。
また、うつ病性障害と適応障害は抑うつ症状の重症度で判断すると誤解されていることもある。しかし、うつ病性障害と適応障害の鑑別は、診断基準を満たすかどうかで判断することになっていて、重症度で区別するという考えは正しくない。適応障害でも、ストレスがあり抑うつ症状が非常に重く、一日中泣いてばかりいるような状態が何週間も続いて、さらに希死念慮もみられるという非常に思い病態を示しながら、夜は眠れるし、食欲もないわけではない、自責感も多少はあるがそれほど強くない、行動抑制も顕著ではないという患者もいて、その場合には適応障害の診断がつく。こうしたことを考えると、抑うつ症状の重症度を基準にして判断すると、適応障害にも起こりうる希死念慮などの症状を見逃してしまう可能性がある。
それはそうだけれども、適応障害という名前の本来の趣旨を考えるとどうだろうか。まあ、法律とは違うので、本来の趣旨とか制定過程とか、そんなことはとりあえずいいのだろうけれども。
最近下火になったが、一時期、「新型うつ病」ないしは「現代型うつ病」「逃避型うつ病」という言葉をよく耳にした。こうした診断名は、「うつ病」という診断で会社を休んでいるのに、自宅では元気に生活していて、人によっては海外旅行に出かけたり、自分の趣味に取り組んだりしているといった、若干批判的なニュアンスで使われることが多いようだ。たしかにそうしたタイプの患者が存在しないわけではないが、画一的にとらえると、誤解を生む危険性があるので注意が必要である。
画一的にとらえているわけではない。拡大解釈でもない。誤解でもない。きちんと鑑別してきちんと扱う。
うつ病の国際的な診断基準が存在してはいるが、わが国では曖昧に使われることが多く、患者が「憂うつです」「仕事をする気力がわかないんです」と一部の症状を訴えるだけでうつ病と診断され、軽症で抗うつ薬が必要ではない患者に対してまで安易に抗うつ薬が使われることがある。
そのように製薬会社は希望したし、そのようにSDM-5は決定したのだ。
仮に似た症状を示していたとしても、発症の契機となったストレス要因は様々であり、患者に応じた治療プランを立てる必要がある。その意味では、「新型うつ病」という名前で、いままでとは違ったタイプのうつ病に目が向けられるようになったのは意味があるが、その一方で、うつ病と診断できない人まで「新型うつ病」と診断してしまうという危険性も存在している。 DSM の診断基準を使えば、仕事を休んでいるときには元気だというのでは、うつ病と診断することはでない。ある時期にうつ病と診断できる症状がそろっていて、それが改善してきたために、職場を離れてストレスが少ないところでは元気に動けるようになったのかもしれない。それでも出社できないとすれば、完全に改善していないのかもしれないし、職場の人間関係がトラウマになっていて復帰しようとすると恐怖心がわいてくるのかもしれない。そもそも、その会社が第一志望ではなかったのかもしれない。もともと怠け癖のある人だった可能性も否定できない。このよに、それぞれの患者にそれぞれの事情や理由があるはずであり、その問題をきちんと考えて解決していかなくてはならない。
うつ病と診断できない人まで「新型うつ病」と診断してしまうのは確かによくないが、診断基準にも問題はあると思う。もっと言えば、精神病の診断は身体病の診断と同じ次元のものと考えてよいのだろうかという問題もある。脳病と精神病は同じ意味なのだろうか。
そうしたときに、「新型うつ病だから...」と言ってそれ以上深く考えなくなるとすれば問題である。それ以上に問題なのは、いかにもその人がわがままだというようなとらえ方をされてしまう危険性がある点である。従来型のうつ病の人は、一般的に中高年層に多く、几帳面でマジメ、なのに対して、「新型うつ病」の人は、他人への依存性が強くてパーソナリティが未熟、自分中心的で他人の責任にする傾向があると言われたりする。しかし、年代を問わず、辛いときには、人に頼りたくなるし、他の人に怒りが向きやすくもなる。それだけ辛いということなのだが、それを「新型うつ病」とひとまとめにされてしまうと、ますます辛くなる。そうでなくても、うつ病をもつ患者は、「怠けている」と自分を責めていることが多い。
それはそうだが、自責する人もいる一方で、あまりに他責で、未熟な人も多いと論じているのだ。
「新型うつ病」が現代若者論として使われる可能性がある点にも、注意が必要である若い人は、元来、経験が少なく、失敗したことがなく、自己中心的になりやすい。筆者がまだ若かった40年近く前には、「モラトリアム人間」「スチューデント・アパシー(無気力学生)」といって、学業にはやる気が起こらないが、アルバイトやサークル、自分の趣味には熱中する大学生が話題になった。いつの時代もそういう若者はいる。「新型うつ病」も、学校が職場に置き換わっただけだとも言える。それを、苦しい病気としてのうつ病に簡単に重ねあわせるのは危険でさえある。
学校が職場に置き換わっただけ、いつの時代もそういう若者はいる?そういう若者とはどういう若者であるかを考えているのではないのか?
うつ病の治療は環境調整、精神療法、薬物療法を統合的かつ効果的に行うが、産業場面での精神的不調では、環境調整が効果的なことが少なくない。たしかに抗うつ薬は効果が期待できるが、SSRI やSNRI などの新しいタイプの抗うつ薬でも副作用が現れることが少なくない。とくに、投薬開始してしばらくの間や、服薬を急に中断した場合にはとくに副作用に注意が必要である。しかも、うつ病を持つ患者のうち 3 分の 1 は抗うつ薬の治療だけでは改善が認められない。 したがって、抑うつ症状が存在するからといってすぐに抗うつ薬などの生物学的治療を行うのではなく、職場やプライベートな生活にストレス要因を把握し、それが改善するようにカウンセリングや精神療法を通して働きかける。産業場面で中程度の抑うつ症状が認められる場合でも、職場要因が影響している場合には、仕事の質や量を調整したり、人間関係の改善を図ったり、配置転換させたりすることで症状が改善していくことは良く体験する。かりに休務せざるを得なくなった場合でも、画一的に原職復帰とするのではなく、患者の病状や発症の状況、職場の受け入れ状態を勘案しながら復帰する場所を選んでいくようにすべきである。そのとき、同時に職員が自ら行っている工夫などを聴きながら、レジリエンスを引き出し活かしていくようにしていくことが望ましい。
うつ病を持つ患者のうち 3 分の 1 は抗うつ薬が効かないのなら、その3 分の 1はうつ病と呼ばないのが妥当ではないだろうか。
『画一的に原職復帰とする』つもりは勿論ないのであるが、職場の事情もある。職場要因があると認定された職場は傷ついている。原職以外の部署で復帰時期を引き受けるとして、そのような余裕があるだろうか。戦力外として置いておくのだろうか。あるいは、原職場と新職場でトレードをするのだろうか。その場合、新職場は戦力低下でスタートしなければならないのだろうか。そのようなトレードを引き受ける上長は部下に支持されるだろうか。
うつ病は、などの概念が主張されたことによる過剰診断や多剤大量処方などの過剰治療が問題視される一方で、治療を受けるのが望ましい状態にあるにもかかわらず受診したり相談したりしない人たちの存在もまた問題となっている。こうした状態を改善するためには、診断名だけにとらわれるのではなく、悩みを抱えた人を全人的に理解して、医療的アプローチはもちろんのこと、ストレスを軽減しながら周囲から適切に支援できる環境を整えていくことが重要になる。
それはそうだけれども、診断名が書類になって独り歩きして、その人の人生に付きまとうのであるから、ことは重大である。周囲が適切に支援できる『余裕のある職場』が得られた人はその時点で幸いである。