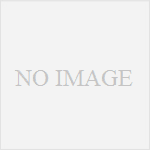内因性うつ病が、ほかの抑うつ病態からはっきりと区別される疾患単位なのか、抑うつ病態の重症例にすぎないのか、という議論には結論が出ていない。
DSM—5のメランコリア基準が大うつ病性障害のクライテリアと重複している。これも、メランコリアを非メランコリアから明確に分離できない一因である。
内因性うつ病の症状には、患者がはっきりと言語化できない「異質性」があり、それを明示的に定義づけることが難しい。たとえば、犬と猫の鑑別を言葉で述べるようなものだ。人間は犬と猫の違いを鑑別診断項目として頭に入れているのではなく、自然な脳の働きとして区別ができている。コンピュータの世界ではディープラーニングの手法があり、ヒトの顔認識などで活用されている。データが集まったところで、ディープラーニングの結果を解析して、鑑別方法を学ぶことができるのかもしれない。将棋の世界でプロの棋士がAI将棋に学ぶようなものだ。
内因性うつ病の主要特徴である『精神運動障害』に基づいて内因性うつ病を定義づける方法がある。
プロトタイプ診断の尺度を用いる方法がある。
精神症状は実体として存在しているわけではなく、医師と患者の臨床的関係から生じた「対話的な共同構成物」という視点から考えれば、身体医学とは異なる水準の「実証性」が規定される必要がある。というような議論もあるが、それは医学の領域なのだろうか。
DSM‒5の大うつ病性障害には、従来の診断学における内因性うつ病と非内因性抑うつの 2 つの病気が含まれている。この考え方を抑うつ病態の「二分論」という。二分論は習慣として定着していて、先輩医師の指導があって、みんな共同で幻想を抱いているのかもしれない。しかし実際の臨床で二分論が妥当だ、治療に役立つと感じて、二分論を踏まえて治療して、一方で、統計処理の時などはDSMー5を使う精神科医もいる。
精神運動制止や生気的悲哀感、感情欠如感、当惑感、気分の非反応性など、伝統的な精神病理学で重視されてきた内因性うつ病の特徴とともに、発症の契機や症状の特徴を『了解できない』という全体的な印象も重ね合わせれば、重症例だけでなく、入院の必要がない軽症抑うつ病態の患者のなかにも、質的に異なる一群があるように思われる。
症候パターンを実証的に同定するためには、因子分析やクラスター分析といった多変量解析が用いられる。
Kendell. R. E.によれば、内因性うつ病に相当するタイプと非内因性抑うつに相当するタイプの 2 つに分ける必要性については合意できるが、両者が別のカテゴリーなのか、あるいは、ひと連なりのディメンジョンの両極なのか、という 2 つのタイプの関係については結論が出なかった。
Nelson. J. C. らによれば、「制止や焦燥といった精神運動障害、環境変化への反応性欠如、重度の抑うつ気分、抑うつ性妄想、自己非難、楽しみに対する興味の喪失」が、内因性うつ病と強い関連をもっていた。因子分析研究の最近のレビューでも「精神運動制止、気分の非反応性」が内因性うつ病の識別にもっとも関連するとされている。
これらをみると、精神運動障害や、気分の非反応性、重度の抑うつ気分、抑うつ性妄想や自己非難などが、実証的に割り出された症候群といえるだろう。しかし、この症候群が他の抑うつ病態から独立したカテゴリーなのか、それとも抑うつ病態の重症例にすぎないのかをどのように検証すればよいのかは明確に答えられていない。
1970 年代に Kendellは、2 つの症候群のあいだに自然な境界が存在するかどうかを数学的に検証するために、二峰性分布(bimodal distribution)という概念を重視した。これは中央に希少点(point of rarity)がある分布をとれば、2 つの独立したカテゴリーが証明できるとする考え方である。この概念を用いて、内因性うつ病と非内因性抑うつのあいだで希少点を証明できた研究もあったが、再現には成功しなかった。
検証するあらたな方法として、Meehl. P. E. が開発したタキソメトリック分析が注目されているが、現時点では、内因性うつ病を独立した症候群であると結論できていない。
1980 年代に Zimmerman.M. らは、内因性うつ病・メランコリアの診断因子として、
1感情障害の家族歴が多い、
2アルコール症の家族歴が少ない、
3反社会性パーソナリティ障害の家族歴が少ない、
4高齢、
5重症度
が高い、
6軽微な自殺企図が少ない、
7夫婦の別居や離婚
が少ない、
8 1 年間のストレスライフイベントが少ない、
9病前のパーソナリティ障害が少ない、
10より多く社会的サポートを得ている、
11認知的な歪み(中立的な出来事を曲解したり、過度に反応したりする頻度)が少ない、
12生物学的異常所見(デキサメサゾン抑制試験など)が多い、
13身体的治療(抗うつ薬や電気けいれん療法)によく反応する、
14精神療法に対する反応が低い、
の 14 項目を挙げた。
DSM‒IIIのほかにも、Research Diagnostic Criteria(RDC)や Newcastle 基準などがあったが、近年では、ほとんどの研究で、DSM のメランコリア基準(メランコリアの特徴を伴う大うつ病性障害)が用いられている。なお、DSM のメランコリア基準は、因子分析などの実証的手続きで決められたものではない。
内因性うつ病患者のプラセボに対する反応の低さが注目されている。
生物学的特徴として注目された、デキサメサゾン抑制試験や睡眠脳波における異常所見は、ほかの精神障害でもみられるため、特異性が限られている。
病前性格をみると、英米の精神医学では、パーソナリティ障害が、しばしば非内因性抑うつの特徴として考えられてきた。しかし、内因性うつ病を積極的に特徴づける病前性格は、実証的に確立されていない。日本では従来、内因性うつ病と非内因性抑うつを鑑別する指標として、執着性格やメランコリー型性格が重視されていたが、ドイツや日本の精神病理学で論じられた性格論は類型論的把握であり、英米の特性論的把握とは方法論が異なる点に注意しなければならない。
メランコリー型性格を実証的に検討するための評価尺度としては、笠原、von Zerssen.D. Stanghellini. G. らによってそれぞれ作成されたものが知られている。ただし、内因性うつ病との特異的な関連が実証されているわけではない。
まずは診断基準の問題である。DSM‒5 のメランコリア基準をみると、8 項目中 4 項目が、大うつ病性障害そのものの基準項目と重複している。したがって、この基準を用いる限り、内因性うつ病と非内因性抑うつを峻別することは難しいという意見がある。
Tölle.R.は、内因性うつ病患者の体験には、「正常心理学のカテゴリーをもっては測り知れないものがあり、私たちは、その中心に近づくことができない。患者自身でさえも、その病後に、自分が克服したその状態に立ち戻ってみるのは困難である。(中略)患者自身にとっても体験として異質で理解しがたいものである」と述べている。果たしてそのようなものなのだろうか。そのようなものだとすれば、そこから先に前進することは難しそうではないか。『はかりしれない』などと言ってしまっていいのだろうか。
DSM‒5 のメランコリア基準にも「はっきり他と区別できる性質(distinct quality)」の抑うつ気分という項目があるが、患者自身が言語化に苦しむような体験を、明示的に定義することは難しい。DSM の注釈をみても、「より重篤で、長く続き、または理由なく現れると表現される抑うつ気分は“distinct quality”ではない」(DSM‒5)、「愛する人の死後に経験するような感情とは異なる」(DSM‒III)という除外的な規定しかない。この異質性は、端的にいえばJaspers. K.のいう『静的了解が不能である』という事態にほかならず、たとえ構造化面接を厳密に用いたとしても、経験をつんだ臨床家以外の評価者がこのような異質性の判断を行うのは難しいように思える。
この異質性の判断が以前は共有できていたが、現在はあまり共有されていないとすれば、それはどうしたことだろう。共有されていないほうが物事を素直に客観的に見ているのではないかとの考えもある。違いを設定して、治療がある程度うまくいく、害は少ないならばいいのだが、害があるとなれば考えなければならない。しかし、実際には二分論には大きな実害はないように思える。
全体的視点と部分的視点
病像の評価に、全体的・直観的な把握は必須である。そこには、患者に面前したときに生まれる治療者の感情的な動きや、「了解できるかどうか」という判断、典型例(プロトタイプ)のイメージをもとにした病態評価、類型論的な性格把握などが含まれる。
異質性の判断も、全体的な把握である。笠原が「個別的・羅列的なメルクマールは、それに先立つ全体認識なしには取り出せない」と述べたとおり、われわれは、チェックリストにある部分的な症状の総和だけでなく、全体的・直観的な把握も考慮に入れて診断しているはずである。
確かに、個別症状をどのようなイメージで総合するかによって、全体像は異なってくるだろう。それが人間の脳の特性なのだろう。しかしそのような先入観を持たないで患者という対象に直面することも必要なのだろう。
カメラのレンズの焦点を合わせるように、診断学も焦点距離があるのだろう。二分論と一元論を両方考慮してみればよいと思う。そして両方の見方で違いがあるかカルテに記載しておけばいい。診断アルゴリズムを明確にしなくても、一歩一歩の手探りで治療を進行させる方法もある。学者としては鑑別診断の構造を明らかにしたいはずであるし、臨床家もそう思うが、確定的な結論が出ていない以上、両方の立場を考えつつ柔軟に対処する方法もある。
精神運動障害への着目を説明する。内因性うつ病の中核的な特徴の 1 つが、制止や焦燥などの精神運動障害(psychomotor disturbance:PMD)である。近年、PMD が電気けいれん療法の良好な反応と関連していることが示されている。PMD はまた、内因性うつ病の症候のうち、ほとんど唯一、定量的に評価できる特徴でもあるため、実証研究の合理的なスタート地点となる可能性をもっている。
psychomotor disturbance:PMD については、この言葉自体が歴史的遺物ではないかと感じる。制止もHemmungのことだけれど、現代の平易な言葉で表現できるだろう。精神と運動についてどう関係していると考えるかでこの言葉の説明が異なっていると感じる。運動の中でも精神から発動している運動について、ブレーキがかかっているとか、エネルギーがなくなったとか、イメージすると思うが、実際の脳のどのあたりが何が起こっているかを考えたほうがいい。人によっては精神や運動の発動性の障害というような意味でとらえている人もいる。それはそれでみんながそう考えるならそれでいいというだけのことだ。
Parker. G. らは、PMD を患者の主観的な訴えではなく、行動面の特徴として評価するための CORE 尺度を開発し、従来の診断基準で診断された内因性うつ病患者の多くを CORE 尺度の得点のみで定義できると論じた。これは、内因性うつ病の主要症状が、PMD と関連していることを示唆している。
大うつ病性障害患者を対象に、CORE 得点と相関する内因性うつ病の主観的症状を多変量解析によって検証したところ、1感情欠如感、2抑うつ性妄想、3当惑感、4決断困難、5他人への攻撃性がない、という5つの症状学的特徴が、DSM‒5のメランコリア基準の項目よりも、CORE 得点と相関することが示された。
Parker らは、CORE 尺度だけでなく、プロトタイプ診断を数値化する評価尺度(Sydney Melancholia Prototype Index:SMPI)も開発している。これは、内因性うつ病と非内因性抑うつの特徴を12項目ずつ列挙し、それぞれあてはまる項目を選択させたあと、最後に、全体像がどちらの類型に近いか、5 段階で評価させる仕組みになっている。日本に普及した「笠原・木村分類」もある。
DSM‒IIIの成立に影響を与えた論理実証主義は、心理学でも物理学でも統一の科学のもとで説明できる、という還元主義に基づいていた。「社会学は心理学へ、心理学は生物学へ、生物学は化学へ、化学は物理学へ還元することができる」という主張である。
しかし精神の症状が、ニキビや腫瘍のような物体ではなく、患者の言語や行動を、評価者が解釈して生まれる「対話的な共同構成物(dialogical co‒construction)」である点を踏まえれば、精神医学における「実証性」が、物理学や化学はもとより、身体医学とも水準を異にするのは自明といえる。ただし、それは精神医学の実証的研究が不可能であることを意味しない。素朴な還元主義に基づくのではなく、それぞれの学問体系に応じた水準で「実証性」を規定することが求められるのである。
この議論では実証性に種類があるという話になっているが、実証性は一つだけだろうとの意見も強くある。我々はまだ脳の問題を解決する方法を手にしていないと思う。昔、天動説を否定して地動説を採用することに大きな抵抗があった。宗教的な思考から自然科学が独立するまで時間がかかった。光学顕微鏡でウィルスを見つけようと頑張っていた。DNAのメカニズムが示されるまでは生命とは何かで迷路に入っていた。
性格研究の方法論には、類型論的把握と特性論的把握がある。類型論では、典型的なタイプにどの程度類似しているかを直観的・全体的に把握するため、「こういう人だ」というイメージがつかみやすい。反面、各類型の中間に属する例を分類できないといった短所もある。
カテゴリーとディメンションの話。内因性うつ病と心因性うつ病の鑑別だけではなく、性格論の中で議論の焦点になる。
Kretschmer. E. の循環病質や、下田の執着性格、Tellenbach. H. のメランコリー型は類型論にあたる。一方、特性論とは、一貫して出現する行動特徴すなわち「特性」を性格構成の単位とみなし、各特性の組み合わせによって個人の性格を記述する方法である。
数量化して個人間の比較ができるために実証的に検証しやすいが、プロフィールが断片的となるため、直観的な全体像を把握しにくい。現代の性格研究の主流は特性論である。